編集長の視点 世界に新たな経済危機 人類はまた立ち上がる
GDPの推移を過去100年で振り返ると、大きく下げた出来事が第一次世界大戦、世界恐慌と第二次世界大戦。第二次世界大戦の後に起こった経済危機は、各国の首脳が協調することで混乱を避けることができたようです。さて、今回のコロナはどこまで影響が残ることやら…。
ニュースを突く 新型コロナ、もう一つの闘い
失業率が1ポイント悪化すると自殺者が1000人以上増えるという傾向が日本ではあるようです。リーマンショックの時も派遣切りとかあって、一年間ぐらい経済が低迷してたような気がするな…。同じ轍を踏まない様、素早い国の企業支援に期待したいと思います。
時事深層 寸断されるサプライチェーン 「大震災」+「リーマン」の衝撃
「これ以上、お客様への供給が止まるようなことがあってはならない。」どっちなんだろう、お客様命なのか、それとも下請けを倒産させないために仕事をするのか…。前者であれば、残念ながら昭和時代の発想。最終製品を作る企業が、すぐに生産調整をすれば大きな混乱はないはずなのに…。東日本大震災で日本企業は何を学んだのやら。どれだけ拠点を分散しても、想定外が来ると止まってしまうことは、よく分かったはず。止まることがありうるという可能性を前提とした上で、ビジネスを考える様にしたほうがいいのでは、と思いましたね。
時事深層 観光に打撃、星野リゾート代表インタビュー 「完全復調は1年か1年半かかる」
私も治療方法が確立されるまでは、この新型コロナウィルスの影響は続くと予想しています。ロックダウンで経済の停滞を気にするなら、まず3密(密閉、密集、密接)だけは罰則対象をすべきと思いますが…。どちらにせよ、まだ日本は対岸の火事と思っている人が多い様に感じる…。
時事深層 新型コロナ、ボーイングを米政府が救済 航空機業界、「官製化」色濃く
737MAXの墜落事故で、財政難に陥っていた米ボーイング社をアメリカ政府が救済するようです。今回の新型コロナがトドメになりましたね。これも大きすぎて潰せないパターンです。金融界も航空業界も国益が関連するので政府が介入するのはわかりますが、小さい企業から見れば不公平にしか見えないよな〜。
時事深層 トヨタとNTT、資本提携の先 章男社長「この指止まれ」の真意
上位概念はNTT。車に関わる分野はKDDI、新規事業やサービスではソフトバンク。 ちゃんとキャリアとの付き合い方を考えていたんですね。
時事深層 世界のスタートアップにも影響か 孫正義の守りと投資家の不安
ソフトバンクグループが出資するスタートアップ、ワンウェブという会社も経営破綻してしまったんですね。ウイワーク投資も失敗したようですし、最近のSBファンドはうまく回っていない感じ…。金儲けに固執するのはやめたほうがいいと思う…。
時事深層 LINEがグループで300億円出資も ウーバーと競わされる「出前館」
フードデリバリー市場は成長市場の1つですが、後発参入が増えると過当競争となりサービス悪化につながりそうで…。まずはシェアをとってから採算を考える戦略だと思いますが、このやり方は問題の先送りに感じて、どうも好きになれないんですよね。PCとプログラム技術があれば、ネットサービスは後からでも参入できるのはわかるけど、もっと他のことに挑戦してもらいたいな〜。
時事深層 レナウン、株主総会で社長再任を否決 欧米ファンドより怖い中国株主
もの言う株主といえば、アメリカの投資会社というイメージが強いのですが、今は中国の投資会社も、もの言う株主になっているようです。日本の変な風土を変えてくれるなら、大賛成。
特集 種は社内にある イノベーションの新作法
オープンイノベーションと最近よく聞きますが、実は思ったほど成果が出ておらず、むしろ欲しいアイデア、技術は自社内に多くあったという事が、最近の調査で分かってきたようです。日本企業が持つ有効な特許は約166万件。うち半分が休眠状態。社内技術や知財財産を棚卸しし、それを有効活用しようとする企業が増えてきているようです。「自分達では気づいてない自社技術の魅力を認知する事も、立派な社内の種の発掘」自分の会社でこういう部署ができたら行ってみたいなー。ビックデータ、ソフトウェアだけでなく、知財ビジネスも大きくなりそうですね。特許が、後発特許に引用された頻度から実力をランキングした表があったのですが、韓国企業のサムソンが1位、LGエレクトロニクスが4位に入っていました。意外にも韓国はアイデア企業が多いんですね。多くの企業は、大抵特許の出願数を目標にしていると思います。今後は他社にどれだけ引用されたか、で評価される様になるかもしれませんね。他、VALUENEXという会社が作った特許の俯瞰図というものがありました。これはどこの企業がどの分野に多くの特許を出しているのかが分かりやすくなっているものです。自分が探してる特許をどこが多く持っていそうか、簡単に見つけやすくなりますね。ビジネスとしては意外と面白いかも。
「知財経営」を能動的にするには、6つのポイントがあるようです。
- 特許・商標の出願部門から、新事業やM&Aを提案する組織へ
- 知財部門が事業部門に組織的、人的に入り込む
- 知財を戦略部門に昇格させ、経営層との距離を縮める
- 他者の技術に目を向ける
- 出願せず、ブラックボックスにする技術を明確に
- 価値の有無を常時見直し、不要な特許は捨てる
スペシャルリポート 欧米勢が商用化で逆転 水素立国ニッポン 揺らぐ先頭の地位
水素は燃やしても二酸化炭素が発生しないし、水を電気分解して液体にできるので運びやすく、また貯蔵できるというメリットがあります。欧米では環境に対する意識が高いので水素利用に前向きですが、日本はなかなか加速せず苦しんでいるみたいですね。水素需要予測は2050年で80EJになる模様。この先30年もかかるようなので、全固体電池に負けてしまうかも…。
ケーススタディー テルモ 成長導いた「脱・自前主義」
GAFAも医療系ビジネスに触手を伸ばしているんですね。彼らが全く手がけていないマーケットは軍事関連ぐらいしか残っていないかも…。
テクノトレンド 1品で済む「完全栄養食」パスタ食べればサラダは不要
ちゃんとした根拠に基づいて作られた完全食なので、身体には悪くはないと思いますが、長く続けると内臓が弱りそう、笑。食事は、人との会話もあったりするので、自分自身はその時間を大切にしたい。シリコンバレーの人は、その時間すらもったいないと思うほど忙しいのかね。
編集長インタビュー カルビー社長兼CEO 伊藤 秀二 新型コロナ、変革の好機に
NB(ナショナルブランド)とPB(プライベートブランド)の話がありました。どちらも変わらないレベルだったら成り立たないと。やっぱりPBは利益を削って販売しているんですね。逆に独自の強みがあり、他社が真似できないだろうという製品はPBを断っていると。「断りきれない場合は、他社品と変わらない物になってしまっていると自覚が必要だ」一人ひとりの自覚が重要です。
世界の最新経営論 オックスフォード流 AIと雇用の未来
「AIが広がっていく将来、我々に必要になるのは、知識量ではなく、変化適応力だ」記憶量はコンピューターには勝てませんからね。変化したときにどう適応できるかがポイントになると。
世界鳥瞰 「回復」掲げて主導権狙う中国
情報を隠蔽したためウイルス拡散の爆心地となった中国ですが、今は、感染国をサポートする良い国にイメージが変わりつつあります。またコロナ後の経済が急回復しているので、中国が世界成長の下支えになるだろうと考える投資家も多くいる様です。中国政府の隠蔽体質さえ変わってくれればな〜。
世界鳥瞰 コロナで強大化する有力企業
今後、財務体力がある会社がコロナで弱った会社を次々と買収し、より巨大になっていくのではないかと言う記事でした。そういうのを防ぐために一時的にカルテルを形成を認めてはどうかと。これはなかなか良いアイディアだと思います。会社が生き残っても、マーケットが死んでしまったら意味がないですからね。
賢人の警鐘 早稲田大学大学院 教授 川本 裕子
論述問題を出すと留学生と日本人では、回答の質が違うという話でした。もちろん留学生の方が優秀。日本は未だ学歴社会の風潮が残っているので、勉強のためにというより就職のためにと思って大学に行く人が多いからではないでしょうか。また日本人生徒に、英語の記事を読んでどう思ったかと聞くと、理解できなかった点を話す傾向が強いらしい。自分もそうかも、笑。でもこれは決して悪い事ではないと思う。きちんと内容を理解した上で、自分の考えを組み立てようとしていると思いますね。日本人は世界的に見れば平均点は高い方だと思います。なので実社会で外国人と仕事をし、こいつら凄いと気付いて自ら勉強するようになれば、きっと能力を発揮してくれると思います。「自分の考えを持ち、それを上下に問わず伝えていく力が各自に求められる」日本企業は、忖度と同調文化が強いので、昭和のおっさんにはなかなかハードルが高いな…。ほんと若い子にはそうなって欲しくない。
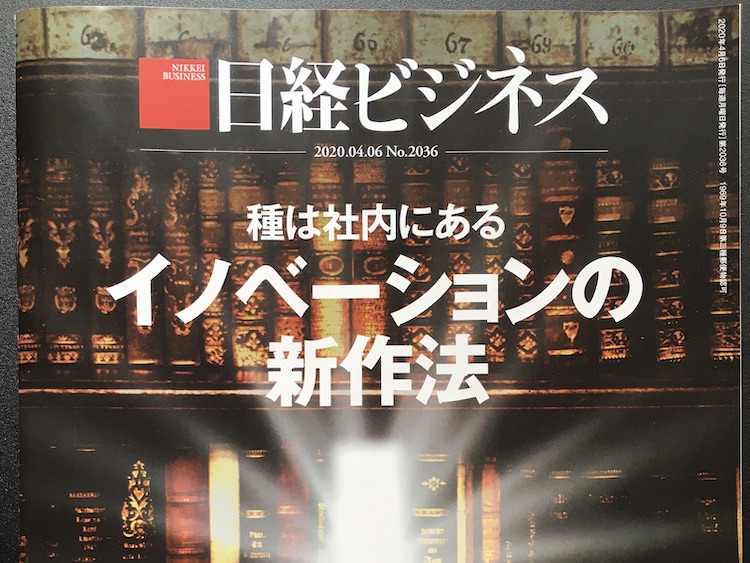
コメントを残す