有訓無訓
「迅速に動く事と、拙速な対応との違いは、目標が明確であるか否かにあります。そして目標を定める時は、利害関係者を多面的に捉えて、この一石三鳥のように皆の利益になるよう考えることが大切」とありました。説明が具体的!聞き手の勝手な解釈はなさそうですね。
編集長の視点
ゴールドマンサックス 投資銀行部門の入社試験がこんなにハードとは…。入社しただけでもエリートなのに、会社に入ってからも常に順位がついてまわるだろうし、休日ってあるんだろうか…。社員が抱く将来の目標ってなんなんだろう。
ニュースを突く
「同社の人類への最大の貢献はヘルスケア分野になる」とアップルは表明しているようです。素晴らしい!どうせなら、もう一歩進んでベーシックインカムを推進して欲しい。病は気からといいますよね。人々が人らしい生活を送れるようになれば、病気になる人も減るのではと思います。
時事深層 紆余曲折の末、マツキヨと経営協議 ココカラが二股に陥った理由
なぜ社外取締役の報酬額がここでピックアップされていたんだろ…。
時事深層 老後2000万円不足問題で注目 中小企業向けイデコに追い風
追い風なんでしょうけど、個人的には今後の日本株に懐疑的…。というのも、売買は超高速でコンピュータがやっているし(長期的な視野で、株の保有をしていない)、資金はクラウドから調達出来るし(上場以外の資金調達方法が出てきた)、そうなると上場の魅力ってあるのかな…と。この先、数十年、日本株はフラフラと横ばいのような気が…。
フロントライン 日本の漫画クールじゃない届け方
日本人、特におっさんって頭かたいし、ビジネスパートナーづくりと交渉が下手ですよね…。「自分達がやらなきゃ誰がやってしまう。だから今自分達が始めないと!」とマネジメントに詰め寄っても、誰も決断せず周りを眺めるばかりで…。で、他の誰が始めた時に大慌てする事がなんと多いことか…。
特集 出来きる若手がなぜ辞めた 本当に効く人材定着の知恵
自分が20代の頃に会社を辞めた理由と、今の若者が辞めたい理由が全く同じ、笑。って事は、やっぱり何年経っても日本企業は変われないって事か。自分の読みが当たっていたので安心しました。辞める理由の本音が、
- 会社が好きだからこそ、会社の衰退を見ていられない。
- 上司にこらえ性かがない。
- 仕事に正義を感じられない。
- 人生を長期的に考えている。
- 世の役に立つ実感がない。
だそうです。離職を減らすのは仕組みづくりじゃないんですよね。会社に対する思い入れはあるので、問題はマネジメントです。上に立つ人が尊敬できないってことになりそうです。
比較的若い会社(1995年以降の創業)や組織がフラットな会社は、離職対策がうまく回っているように感じますね。問題は、昭和以前に設立された組織の階層が厚い古い大企業かな。ここには若い人が務め続ける吸引力はもうないかと…。ベテラン層が多いからポストが空かない。すると、金魚のフンのように権力について回る忖度上手が出世していく。ポストにつけなかった人は、会社への不満をつい若手にこぼしてしまう。この環境が若手の離職を加速していると思います。
どうすればいいか?真っ先に行うべきことは、今のマネジメントの再評価。能力の無い人にはラインから外れてもらい、実力のある人にマネジメントになってもらいましょう。で、ポストが無いなら、輪番体制にする。中年層にも刺激となり、若手のやる気も上がると思います。
スペシャルリポー 規制緩和で取り組み拡大 宅配便はタクシーが配達 貨客混載、地方を救うか
たまたま輸送物に焦点があたっているだけで、大きな荷物を持った人の移動と考えれば、これってMaaSそのものと思いました。
ケーススタディー 日揮
「相手には相手の論がある。相手の背景を尊重しながらロジックを組み立てろ」「問題が起きそうと思った時は9割の確率で起きる。対応策を準備しておくことで相手からの信頼を獲得しつつ、期限に間に合わせる」 こういう肌感覚は、現場の前線でしか経験を積めません。若いうちから経験をたくさん積めるこの会社が羨ましいです。
「仕事を遂行するには、パートナーが必要で、関係を深めリスペクトを忘れないためにも現場で、顔を合わせることは重要」と社長の言葉にありました。今は、電話会議のようなツールもありますが、半年に一度は、お互いにパートナー同士が顔を合わせる事も必要と思います。
フロントランナー フジワラテクノアート
日本酒も今や機械で匠の味が再現できるんですね。味が管理しやすくなり、供給も安定するのであれば、自動化も良い事かな。
テクノトレンド 陸海空に新モビリテ 開発進む空飛ぶクルマ
だから、それは1人乗りのヘリコプター、笑。住宅密集地での飛行は、危険だから。
経営教室 反骨のリーダー 金車グループ(台湾) アルバート・リー
備忘録として。後発組の勝ち方
- 参入するなら、全体のパイが大きく伸びしろのある市場にする
- 先発組のノウハウを最大限生かす
- 常識にとらわれない逆転の発想で欠点を利点に変える
- 目先の売り上げのために安売りはせず、長期視点でブランドを育成
世界の最新経営論
AIは、「人間の意思決定の一部に関わり、判断をより良いものにすることが、出来るツールといえる」とありました。そうあって欲しいものです。
賢人の警鐘
「画期的な製品、アイデアは若く活力のある社員によって推進される」とありました。ん〜、アイデアは年齢関係なく出てくると思うし、別に若手が入ったからといって、それが刺激にはならないような気が…。知り合いの外国人に言われたのが、「日本は長期連休がない。頭がリフレッシュできないから、発想が固くて良いアイデアが出てこないんだ」と。もっと休みを増やせば、少子化対策の妙案が出でくるかも…。
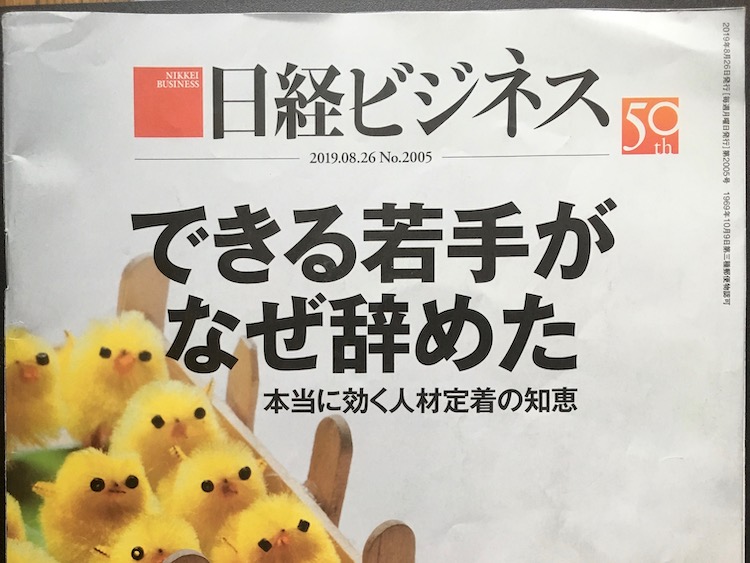
コメントを残す