編集長の視点
「ボケた経営者が社内を混乱に陥れる」。実際に起こってるようです。若い社員に「あの人、老害だね」と陰口を叩かれる前に、自分は会社を去ろうと思っていますが、去った後に、自らが辞める選択したことを忘れて、また「俺を雇え」という人もいるようで…。ボケって怖い。例え、自分がボケて暴走したとしても、それを止めることができる組織構造、ルールの策定が大切だと思いました。
時事深層 海外工場で相次ぐ撤退・縮小 ホンダ現地化優等生の誤算
車って昔ほど必要じゃないよね、とよく聞くようになりました。もちろん今でも車好きな人もいるのですが、普通は、細かく性能、機能を比較しないはず。となると、デザインが重要になると思うんだけど、どうも最近の日本車のデザインは良いと思えない。箱っぽいというか。。あくまでこれは個人の感想ですが、車を「運転している」のではなく、ちょこんと「乗っている」ようにしか思えてなくて。これが車を所有する楽しみを減らしているような。。。そっか、「ずーっと眺めていても全然飽きない」これが所有ってことか。
目覚めるニッポン 中国に抜かれる危機感を
「一度、駄目になれば危機感を持てる」とありました。日本はものにあふれ、大方の人がそれほど不自由でない生活を送れるので、危機感を持つのはまだまだ先なのかなと思います。
時事深層 小泉進次郎氏も起用し総仕上げへ 内閣改造に透ける安倍首相の本音
年配政治家はいつも自分のポストばかりを心配。こんなんじゃ、小泉さんを使ったとしても、若年層の投票率が上がらないですよ。
フロントライン 独VW 背水の大衆EV
2021年に、18年と同じCO2排出量だと1兆円の罰金になる?環境保護も大事だけど、そもそも会社をつぶしてしまうと、もっと環境保護が遅れてしまうような…。桁違いの罰金は、少し考えものかもしれない。
特集 「踏み間違い」だけじゃない 判断力低下社会
自分の身に降りかかりそうな問題は、突然上司がボケて、自分が首になったりするぐらいかなと思っていたけど、知らないうちに親が高額商品をローンで購入してしまったとか、万引きをやるようになってしまったとかいうこともあるのか。こりゃ大事だな。。。三菱UFJ信託銀行が販売する「つかえて安心」という商品が売れているみたいです。親の口座の入手金を親族が見守るというサービスです。即座に親族へ連絡が届くようになれば、オレオレ詐欺対策にもなるような気がします。
スペシャルリポート 胎動する経済回廊 米中摩擦が追い風に
うまく波をとらえている人は、米中摩擦ですらビジネスにしていますね。島国日本にいるとなかなか分からないけど、国境をまたいだ幹線道路(南北経済回廊、東西経済回廊、南部経済回廊)沿いが発展しているのをみると、大きなビジネスのうねりを感じます。
スペシャルリポート 勃興する投げ銭型ライブ配信市場
思った以上にライブ配信の市場は大きいようですね(自分はとても恥ずかしくてできない。。)。ライブ配信だけで月1000万円稼ぐ人がいるっていう話だからすごい。誰もが、自分を世界に表現できる時代か。。自分も将来のために何か特技を見つけようかな。。
スペシャルリポート 激化する2021年採用戦線
開発設計系の給料は、むしろ個別で設定し、年契約にしたほうが良いと思いますね。ただ、給料の話でいつも忘れがちなのは、人の品格について。自分の経験上、給料をたくさんもらっている人ほど、人間性にかなり疑問を感じる時が多いです。わがままを貫き、組織を混乱させ、最後は会社を去っていく。そんな新人は不要です。30過ぎても勉強する人は伸びます。まず、そういう人を選択する人事の眼力があるか。次に、そういう人に育て上げる能力がマネジメントにちゃんと備わっているかが重要ではないかと思います。
テクノトレンド VRで社員教育!顧客サービス 恐怖も感動もリアルに体験
普通のテレビでする家庭ゲームでも、最近のは高いところから落ちる時、かなり肝を冷やします。笑。仕事の危険をVRで、事前に体感できるのは、いいアイデアですね。
編集長インタビュー マツダ社長 丸本明
上の時事深層でも書きましたが、車のデザインって重要だと思っています。マツダの車は、技術以外にデザインからも「自分が車を運転している」って感じがするんですよね。今は、販売が伸び悩んでいるようですが、価格を下げてしまうとブランドを毀損しかねません。何とかここは踏ん張って、ドライバーが「運転している」という気になれる車を作り続けてもらいたいと思います。
賢人の警鐘
確かに、最近は、セールやポイント還元などが頻繁にあって、本当の価格がいったい何なのか分からなくなっていますね。安く売るよりも、私は適正であることが重要だと思っています。でないと、いつまでたっても自分たちの給料が増えませんから。記事にあったように、経営者には、「成功している企業は何をどうしているか」を継続して考えてもらいたいと思いますね。
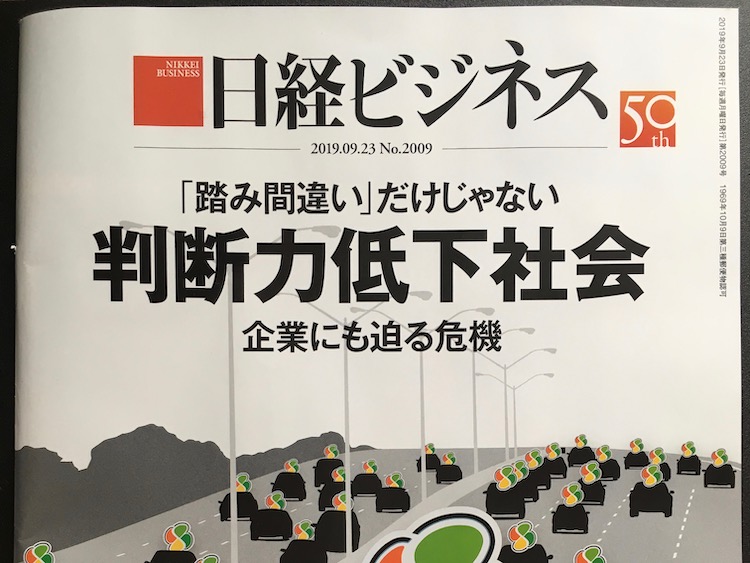
コメントを残す