有訓無訓 カゴメ 会長 寺田 直行
社員一人ひとりが変わっていくには、「生き方改革が必要」という話。個人の可処分時間の過ごし方が個人を強くし、それが会社を強くすると。会社人間では、頭が硬くなるぞってことか…。こういう経営者がもっと増えて欲しいね。
時事深層 米アップルが「Mac」も自社開発品に転換 半導体で競う世界、岐路の日本
外ファブじゃなくて、設計開発も自社か…。自動車業界でも同じような動きになってますね。半導体メーカーが主導権を持つのを嫌ったかな。日本の半導体メーカーも自社ファブを持つことを止め、設計開発に特化していたらもう少し変わったかもね。半導体設計者には、メーカーに転職できることになるから嬉しい話になるのかな。
時事深層 コロワイドの株主提案を株主総会で否決 大戸屋HDが勝てた本当の理由
コロワイドの大戸屋買収関連。コロワイドが株主優待を広げる提案をしたけど、株主総会が終わってみれば否決。敵対的TOBを仕掛けるとコロワイドが言ってしまったのが失敗だったかも…。株主にしてみれば、TOBでプレミアム価格が乗った後に売った方がお得だもんね。さてどうなることやら。
時事深層 紙需要、「書く」から「包む・拭く」にシフト 大王・王子にも”脱汎用”の波
コロナで衛生用品向けの業績が伸びているようです。またプラ容器の代替品も開発が進んでいるようですね。コロナでテイクアウトが増え、プラゴミが増えたって聞くし。汎用品から高機能品へ、製紙業界も次の柱を探す動きが活発になっています。
時事深層 コロナが変えるグルメサイト勢力図 無料で集客、インスタの破壊力
お店側としては、よく分からない書き込みが増えてしまった食べログに毎月数十万円を払うよりも、無料のSNSで、顧客と直接つながったほうが嬉しいからね。インスタではテイクアウトやデリバリーの受付を始めたみたいだし、外食もデジタルでドンドン変わってきてる。
特集 もうひとつのESG コロナで見えた「優良企業」と「幻滅企業」
最近の企業評価基準は株主第一主義からESGに変わってきています。今回のコロナのような時には、「もう一歩踏み込んだ自己犠牲を買って出る企業の存在が社会に求められるのではないか」と。武士は食わねど高楊枝。日本人はその気概が昔からあったと思う。コロナの対応がよかったと言われる企業と、その社長の言葉をご紹介。
- 三幸製菓 佐藤CEO 県内で正社員含め80人の大規模雇用「周囲が大変な状況に陥る中、自分たちだけが無事、つまりは『難を逃れていていいのか』と言う思いがあった。」
- ライフコーポレーション岩崎社長 緊急特別感謝金を従業員に還元配布 「会社は誰のものか論議になることがありますが、米国流の『会社は株主のもの』ということではないと思っています。お客様と従業員、取引先の3つの循環がうまく回って、それが利益となり、おこぼれが配当として、株主や創業者に落ちてくる 」
- まるか食品 丸橋社長 巣ごもり消費で出荷増 グループ社員約150人に1人10万円ずつ特別感謝金を支給
- 城南村田 青沼社長 フェイスシールドを医療や介護の現場、手話通訳者らに無償提供 「出社の自粛やテレワークに移行せよと言われても町工場にはそれができない。それが申し訳なくて。皆さんが足りなくて困っているものを一生懸命作れば、少しは許してもらえるのではないかと思った」
- アパホテル元谷社長 ウイルス感染者のうち軽症や無症状の人の一時的療養先として、自社のホテルを提供 「経営をしていると、『ああ、天に助けられたな』と思うことがたくさんある。やはり人には役割というものがあって、その役割を正しく果たしていれば、いざというときに大きな力が助けてくれる。私はそう信じている」
- アイリスオーヤマ マスクの増産 「企業というのは本来、人々を豊にして、助けるために存在する。ただ、人助けだけでは組織は維持できないから、人助けの代わりに利益と売り上げを少しいただく。」「組織である以上、効率化を追求するが、その目的は株主利益の最大化ではなくて、世の中の幸福の最大化だ」
上記のような会社がある一方、危機によって自分の会社、トップの本性が分かり、がっかりした人も増えているようです。やはりトップ次第ですね。今や、ネットを介して従業員の不満が簡単にオープンになる時代。そういう会社は、長くは生き残れないようになってくるんだろうな〜。
スペシャルリポート 温暖化防止を阻む「認識」と「政策」の壁
まず、どこの国のどの分野が多くCO2を排出しているのか、というのを見えるようにできないものかな。理屈では、材料の購買履歴から排出量が予想できると思うんだけど。今は罰金を取りやすい業種が叩かれているような気がするし…。本当は罰金に頼るのではなく、自然と減らさなければならなくなる仕組み作りができるといいんだけどね。
ケーススタディー AGC 縦割りは若手が壊す
他事業部との交流を増やす活動をしています!とは名ばかりで、実際は、上司のお気に入りが若手の選抜メンバーとなり、クローズした空間で世間のウケが良いことをしているという話も聞いたりするけど、この会社はやりたいという人にはちゃんと平等にチャンスが与えられているようですね。最後に少し記事になっていましたが、経験と勘をデジタル化し、複数の工場を1カ所で管理するスマートファクトリーにも取り組もうと考えているようで…。進んでいますな。
テクノトレンド 鉄道をより安全に、より快適に ARで製造管理、3Dで軌道計測
単調な作業ほど人間のミスを0にすることはできないと思ってます。今までのやり方は徹底したマニュアル化で作業漏れをなくす。ただ、このやり方だとマニュアルが膨大になるんですよね。将来、作業員の減少で一人頭の作業量が増えてくることも予想されるので、ARの画像解析によるミス削減は有効な手段だと思う。懸念はデジタル化する時に必ず付きまとってくるセキュリティかな。
編集長インタビュー 村井 満 Jリーグ チェアマン 再開は中断より難しい
デジタル化で手応えが出ている様子。Jリーグに関わらず、日本のスポーツ界ってデジタル分野に弱い気がする、笑。他のスポーツもJリーグを見習って、コロナの中でも頑張って欲しい。
世界の最新経営論 INSEAD流 リーダーシップの心理学 経営心理学による危機対処法「耳障りな意見」を集める
リーダーが恐れを克服するための方法として、認知行動療法とマインドフルネスの紹介。
- 認知行動療法の3ステップ 自分の考えに気づく→考えを修正する→考えを変えることで行動が変わる
煩わしいなら、
- マインドフルネス 注意を払っていくプロセス→厳密にいいか悪いかを判断しない→自分の心身、内面で起こることを注視する
自分の周りの管理職にも読ませたい記事だった、笑。上位職のご機嫌を損ねないように動くものだから、無駄仕事が増えてホント厄介。というか、それは上位職の問題か、笑。
世界鳥瞰 中国新興EC、急成長のひずみ
時価総額で米ウーバーやソニーを上回る中国の新興EC企業ピンドウドウ。実態は、損失を垂れ流ししながらの販促。それを補うために定期的に資本市場からお金を調達。中国スタートアップの常套手段、採算度外視で走りシェアを取ってから考える、ですな。お金があるところにはあるもんだ。
賢人の警鐘 早稲田大学大学院 教授 川本 裕子
「人間の周囲『ラスト1m』の仕事はなかなかデジタル化できないことも明確になった。具体的には、看護、介護や育児などだ」「しかしラスト1mの大事な仕事の報酬は低く放置されてきた。社会生活を支える最後のとりでとして、もっと手厚い支援をし、金銭的にも報いるべく転換すべきだ」なぜ、介護、介護、育児の報酬は低いままなんだろう?昔なら同居している親がやっていたことで、誰にでもできる仕事だからと思われているからかな?
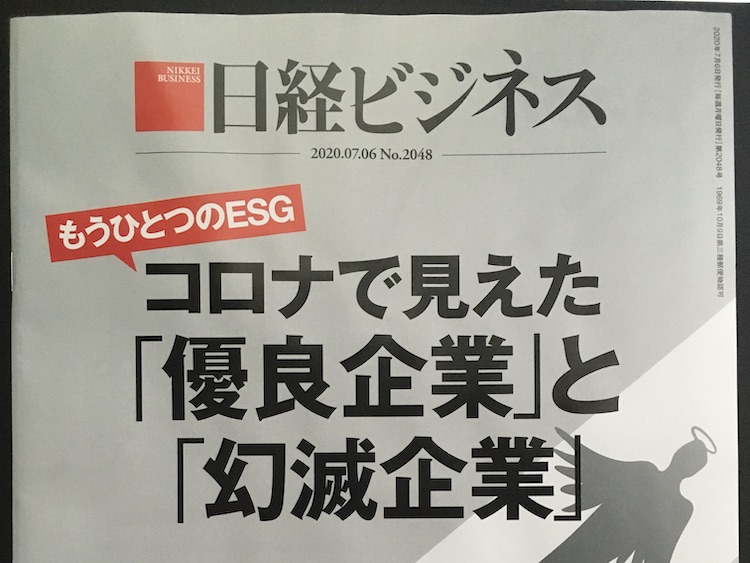
コメントを残す