有訓無訓
「考えの元になるのが知識で、その知識の取捨選択で、その人の思考形成やひらめきにつながる。知識は覚えればすぐに使えるが、ひらめきには結びつかない。自分で考え失敗することで、人はひらめき、成功にたどり着くことができる」とありました。
最近、仕事にAIの導入か進んでいます。知識や計算スピードではAIにかないません。AIとの共存を考えるのであれば、どう使うのかを考える力が必要になってくると思います。あと気をつけなければいけないのが、入力するデータです。無作為でバイアスがかかっていないデータをどれだけ選択出来るか。「選択」そのものの重要性が問われてきますね。
時事深層
地銀再編に狭まる包囲網で、政府は 「独占禁止法の例外規定を盛り込んだ新法か、独禁法を適用する際の新たなガイドラインを作る方針」のようです。ん~、特定(地方銀行)の人を助けるためにルールを変更って、何かがおかしい…。独禁法って大手企業を優遇するための法律? 公平な競争のためにあるようですが、何をもって公平としているのか分からなくて。例えば、どう考えても原価割れの価格を出してくる企業(大手企業)ってあると思います。その大手が中小企業を駆逐しても、潰された中小企業には何も政府の支援なし。だけど、その大手が経営で行き詰まると政府が支援をする。しかも税金を使って。不公平な自由競争としか思えないんですよね~。
テクノトレンド:技能の継承にデジタル活用
「ベテランと、新人の視点の移動量の違い」とかが表にしてありました。これは一例だと思いますが、技能継承と生産性向上は分けて考える必要があるのかな~と思いました。なんか人間を「熟練したロボット」に作り上げているような感じがして…。なぜその動きになるのか、そこに行き着いた背景の習得も技能継承には必要だと思います。
編集長インタビュー :佐藤おおき nendo 代表取締役チーフデザイナー
「デザイナーはシェフではなく主婦のような仕事。冷蔵庫に眠る食材でもおいしい料理を作れると気づいてもらうのが僕の仕事です」とありました。ほとんどの企業は改善しなければいけないポイントや、アイデアを持っている人はいると思いますし、またどんな会社にもそれを実行出来る人が必ずいると思っています。なので外部に頼らなくても改革は出来るはずなんですが…。傍白にあったように、組織や人間関係、前例踏襲など競争力を自ら削ぐ悪弊があるため、いつまで経っても、社内の人材を有効活用できないんですよね…。
賢人の警鐘
「社会取締役を、何人、何割揃えるか等より、質の向上の方が最優先」その通りだと思います(女性管理職を増やそう、という事にも同じことが言えるような気がします笑)。そもそも社外取締役を入れるようになったのは、ガバナンスが働くようにするためだったと思いますが、自分の知人を社外取締役メンバーにすることが増えているようです。本当にガバナンスが働くのかな…。
公平な判断のために、社外取締役の選定や、社内の管理職の選定は公平な判断という意味ではAIに任せるのも一つの方法かもしれません。
でも、お利口さんは、一足先に手を打つんでしょうね。例えば、最初っから自分達が選ばれるようなバイアスのかかったデータを入力するとか、最終的には人間の補正が必要だ!とか言って自分の意見を最優先にするようルールを作り直すとか…。
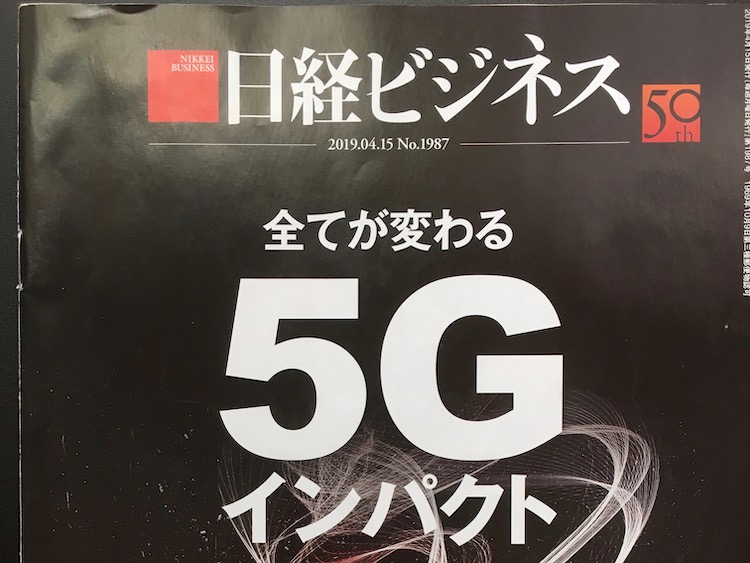
コメントを残す