有訓無訓 一橋大学名誉教授 関 満博
昔は、やるべきことが分かりやすく、みんな頑張った分だけ給料は良くなったけど、今は昔のやり方が当てはまらなくなり、自ら新しい解決方法を見つけなければいけない時代になってきた、と。いよいよ上司のイエスマンで出世をしてきた人達では、経営をきちんとコントロール出来ない段階に入ってきましたね。でも、日本企業のリストラはいつも末端からだからな〜、嫌になっちゃう…。
ニュースを突く 福島原発、見えぬ国の長期方針
原発から出てくる汚染水は1日170トンもあるんですね。てっきり上手に処理されていると思っていましたが捨てられずにいて、2022年夏には保管場所が満杯になるとか。また汚染された土は約1400万㎥もあるようです。こちらも30年後に県外で処分する事になっているけど、その廃棄方法は不明のまま…。30年後に誰かがきっと解決してくれるだろうという、いつもの問題先送りになっていますね…。
時事深層 働き方、サービス、教育…… 新秩序の模索が始まった
台湾では、マスクの転売を防ぐため、政府がITをフル活用。日本でいう健康保険証のようなカードあり、それで購入制限をし、個人の買い占めを防いだようです。日本とは大違い…。この新型肺炎は長引きそうですね。今を堪えて残存者利益を狙うか、それとも早い段階での撤退を考えるか…。とりあえず、早く収まって欲しいと願うばかりです。
時事深層 業界大手と提携協議開始を発表 TOB断固阻止、執念の前田道路
500億円を超える特別配当をすることにした前田道路が、さらにNIPPOとの資本業務提携の協議を始めると発表。なぜ、そんなに前田建設との提携を嫌がるんだろう…。
時事深層 津賀社長続投含む役員人事発表も パナ、苦悩透ける唯一の「昇格」
近年、不採算事業(半導体事業の売却等)の整理をしていた片山氏が評価され昇格。撤退戦略って日本企業が一番下手な分野です。こういう仕事を担当している人の評価は、もっと上げてもらいたいね。
フロントライン 「一般人マスク不要」発言の真意
新型コロナウィルス対応で、トランプ大統領がリーダーシップを発揮してるようです。感染者の治療を優先し、医療従事者の安全を確保しながら完治を促す。珍しくまとも、笑。とはいえ封じ込めは思うように進んでいない感じ。今後どうなるか予断を許しません。
特集 社員はなぜ育たない 危機を乗り切るリーダーの作り方
「到達不可能な目標はかえって優秀な候補者を脱落させることになり、結局、周りにはイエスマンばかりでトップの暴走が止められなくなる」「ポストが減って、部下を持った経験の少ない社員が増えたため、チームを統率できる人材が育っていない」言い訳とも取れるような問題がどこ企業もあるようで、笑。で対策がいくつか紹介されていましたが、一番進んでいるなと思ったのがIBM。「意欲がある社員には能力を問わず学ぶチャンスを提供している。最近では、AIや脳科学の知見も取り入れ、より客観的な評価育成プログラムを提供できるよう進化させている」いいですね〜。若い社員に対しエリートコースを設ける企業もあるけど、大概が社長や管理職のお気に入りだから個人的には好きでない。あと「リーダーの器量以上の組織は絶対にできない」と。自分よりも優秀な人を採用すると評価が上がるような仕組みにしないと…でも、日本企業じゃ無理だわな…。
陸上自衛隊には「指揮の要訣」と呼ばれるものがあるようで、備忘録として。
- メンバーの状況掌握:メンバーの一人ひとりが役割を果たす上で問題を抱えていないか確認。
- リーダーの企図:企図とは細かな指示の背景にあるもの。これを説明すれば部下は自発的に動く。
- 適時適切な指示で行動を統制すること:命令には一点の疑義もないように。
どれも、最近の分業が進んだ組織では欠けているものばかりですね。
不思議に思ったのは、リーダー育成に頭を抱えている企業もあれば、サイバーエージェントのように、社長をバンバン輩出している企業もあったりして、すいぶんと考え方が違うものだなと思いましたね。リーダーと言っても、会社規模や、若手、中堅、社長候補では、求められる物が違うので、今回の記事は、あくまで参考程度というこで。
逆・タイムマシン経営論
最終回は、飛び道具トラップに陥らないための回避方法が書いてありました。
- まずは自社の戦略を固めること。
- 飛び道具とセットになっている、成功事例がなぜ成功したのか十分に理解すること。
- 飛び道具を抽象化し、理論でその本質をつかむこと。
これが分かっていても、罠にかかる人がいますから、笑。飛び道具を導入して失敗した会社は、どうやって導入を決定したんだろう。ITサポートを一人でやっていた?ITリテラシーが低い経営者の鶴の一言で決まった?背景が知りたかったな。
ケーススタディー JR貨物 脱「お荷物」、外部人材が牽引
「何をやっても無駄だ」こういう言葉が出る人は、会社を良くしようと過去努力したんだけど、結局は当時の反対勢力に妨害された人達なんでしょうね…。やるせないですよね。この会社はぜい肉が多いので、すぐに筋肉質になれそうな感じがしました。
テクノトレンド 味覚のデータ化 「ビールに枝豆」の相性も証明
味も、デジタルで可視化の動きが加速しているという記事でした。人間にベストの味が見つけられるようになると、どのメーカーが作っても似たり寄ったりの味になってしまうのでは?と思うのは私だけ、笑。評価者の感覚がメーカーの味になるってことかな?
編集長インタビュー 寺畠 正道 日本たばこ産業(JT)社長 紙巻きの成功体験捨てる
「経営理念は共通の理解を持ってもらう。そして大事なのは(買った側も買われた側も)フェアに扱うことだ」 M&Aの基本ですね。
世界の最新経営論 クレディ・スイスには投資基準も うわべの「環境配慮」は×
ここでも企業の透明性の重要さを挙げられていました。うわべだけの環境配慮は、内部告発者により瞬時にSNSで噂が世界中に広まるよと。対応を一つ間違うと大きなダメージを受けかねない時代になってきています。
世界鳥瞰 中国、監視技術で新型コロナ対策
監視技術が新型コロナの封じ込めに役に立っているのは分かるけど。携帯を追跡して身元を確認しているとか、アプリから何を買ったかとか、どんな会話をしているのか、全部漏れているそうです。ちょっと怖い…。
賢人の警鐘 三菱ケミカルホールディングス 会長 小林 喜光
「テクノロジーが究極に進化する世界では、哲学の重みが確実に増すのは間違いない」私もそう思います。倫理、道徳感を企業の人の評価項目の一つに取り入れるべきだと思います。「現状、既得権を守ることを重視したり、昔ながらの研究に固執したりするケースが目立つ」 やっぱり自分の身が一番可愛いってことですよ。会社のために全体最適をしているか、という項目も評価に取り入れるべきだと思います。
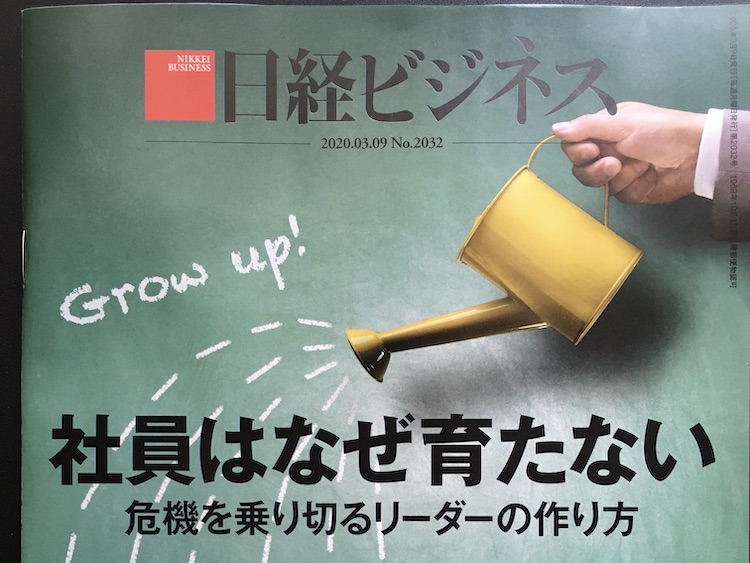
コメントを残す