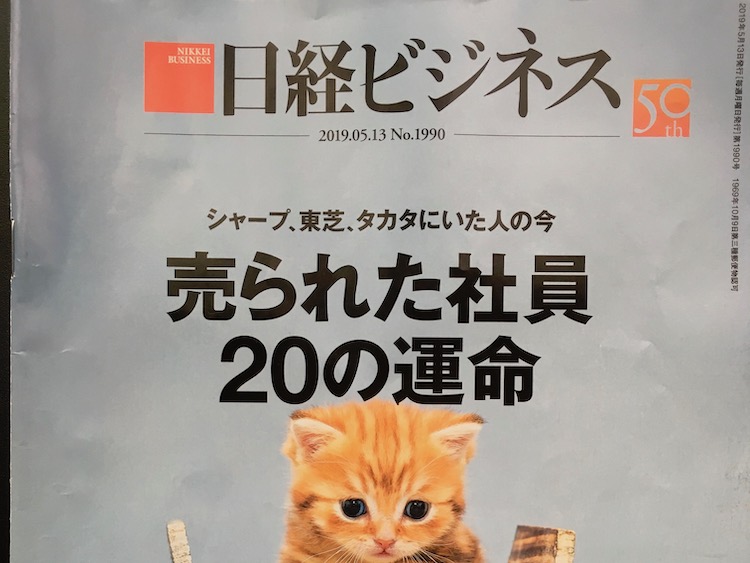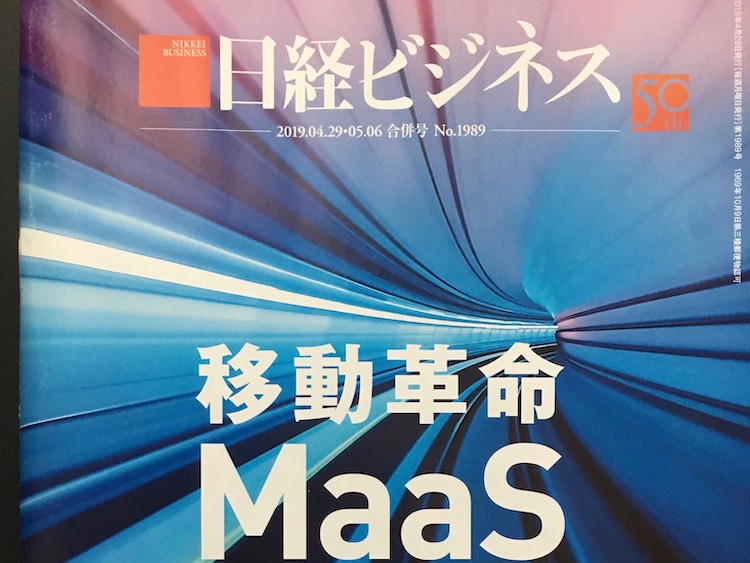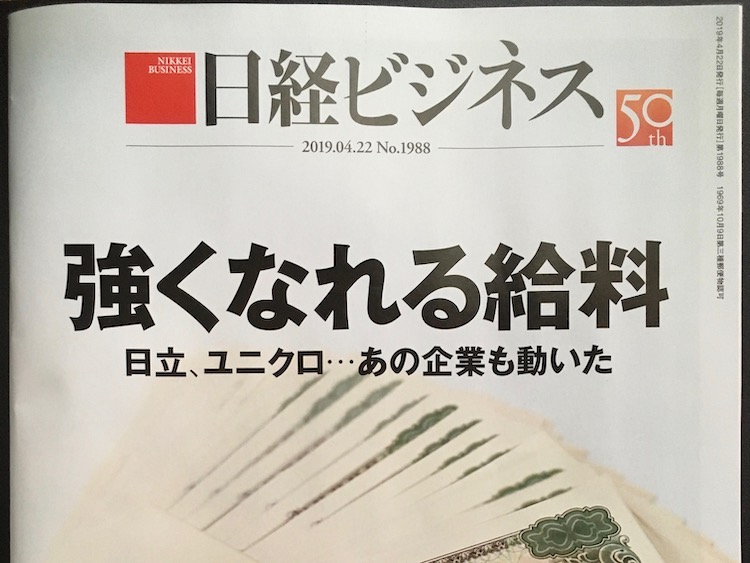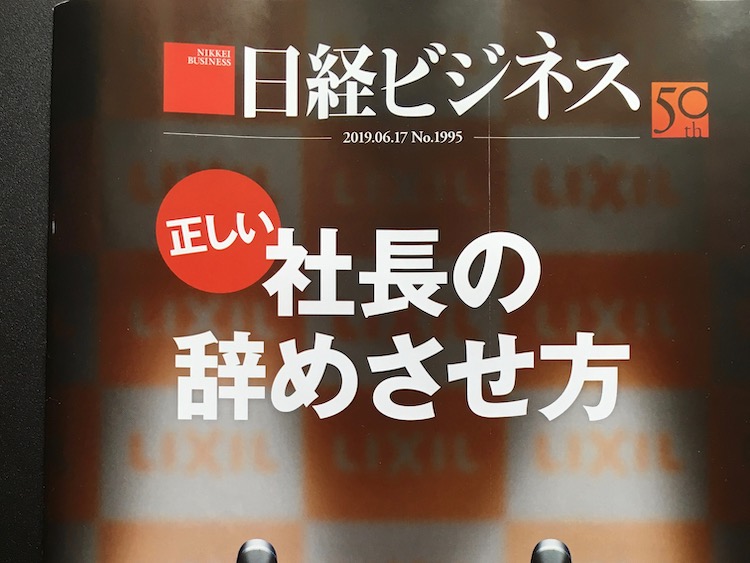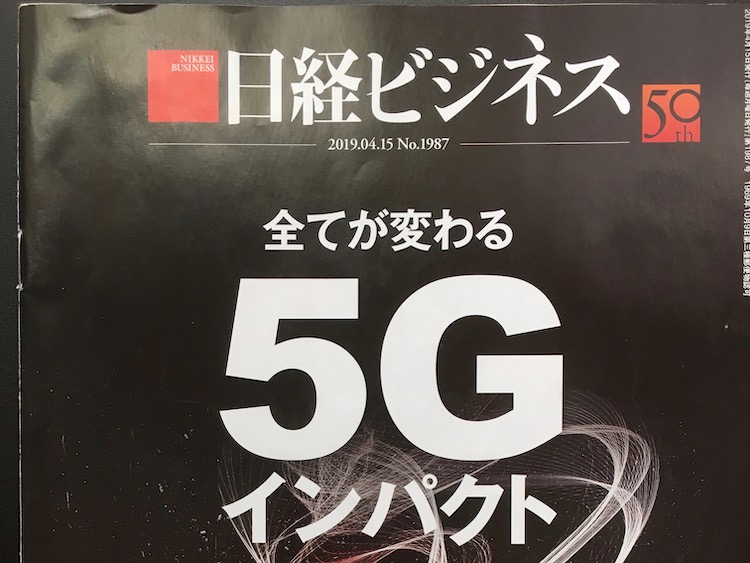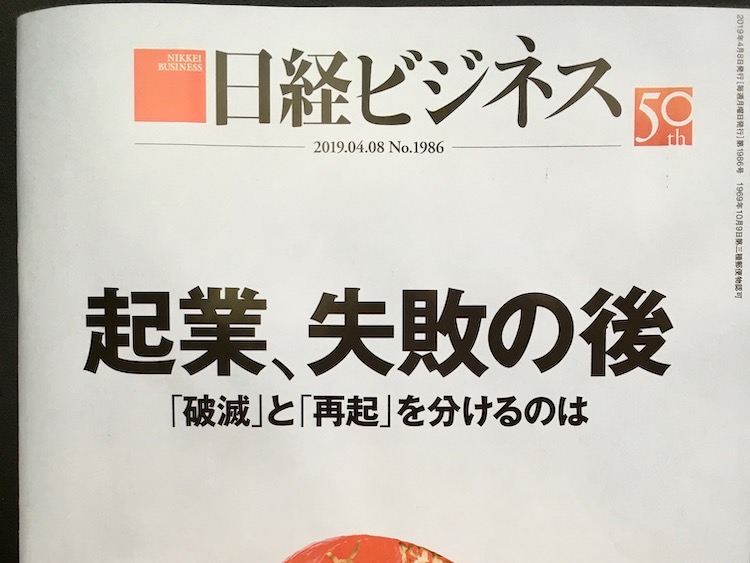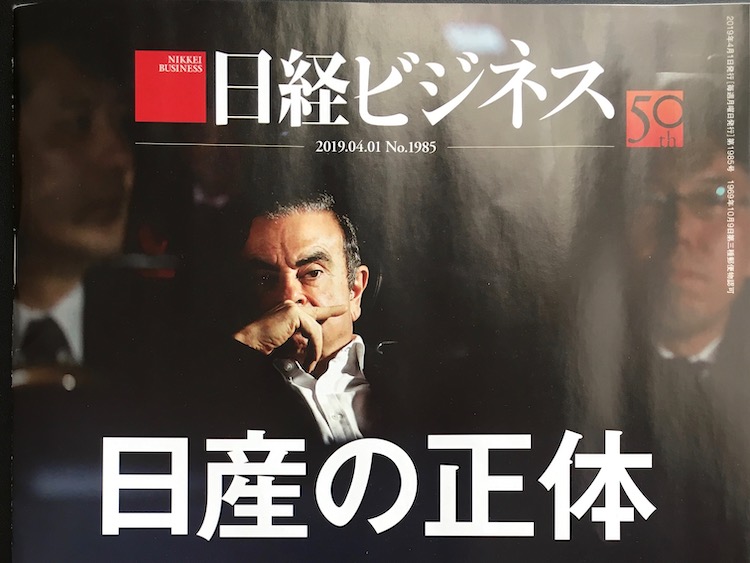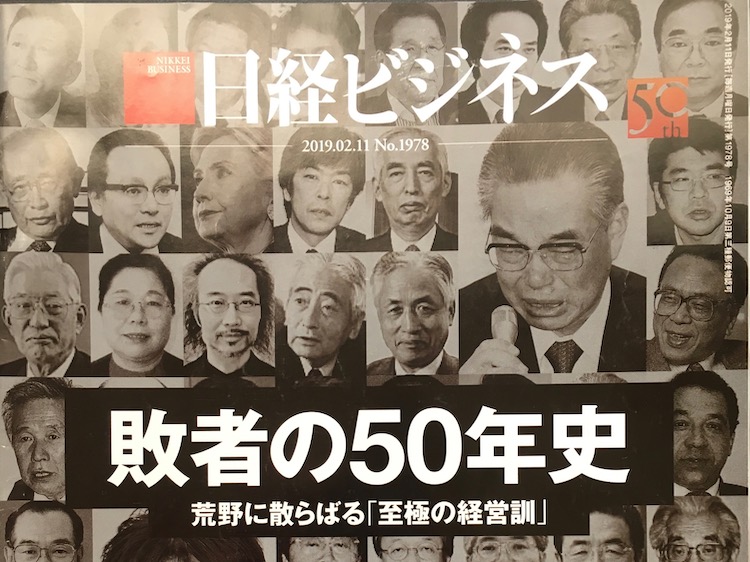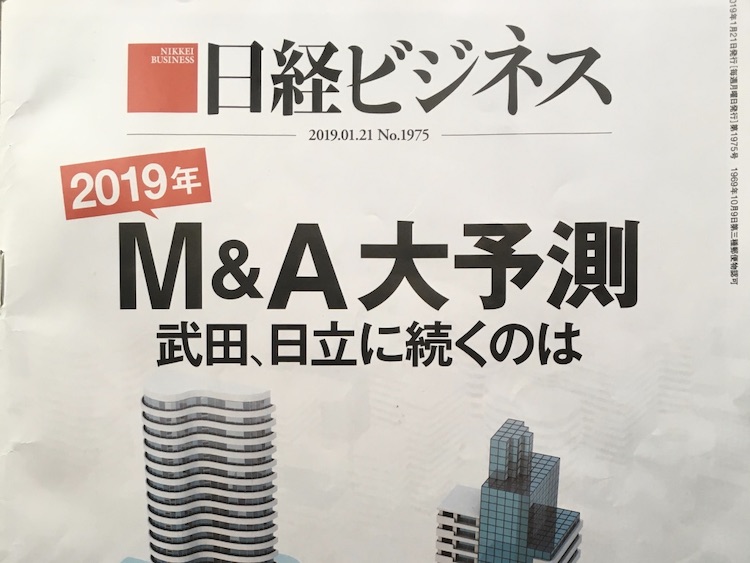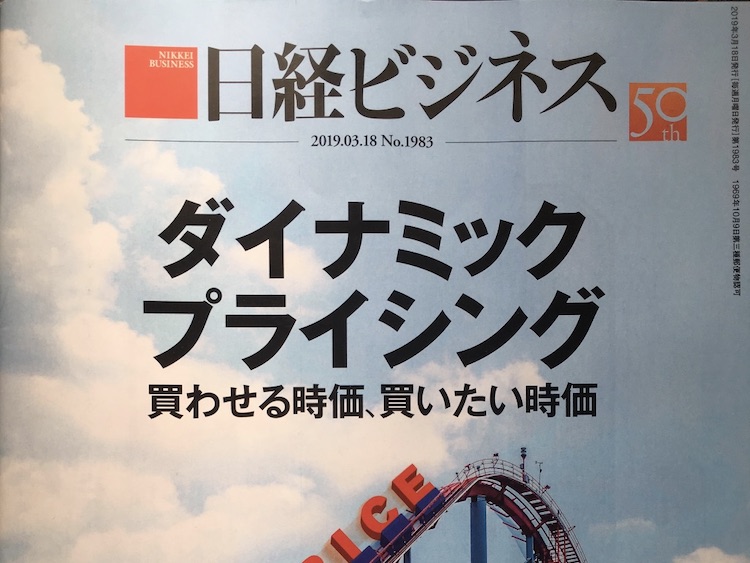有訓無訓
認定NPO法人 本の学校の話がありました。知識の習得や自己啓発、内容をまとめ人に伝える力を付けるためにも、本を読むことは、大切だと思います。若いころは全然思いませんでしたが、30代後半になった頃、活字って必要だな、と思うようになりました。
ニュースを突く 外国人材活用特定技能の課題
人手不足の対応として外国人労働者の受け入れ拡大が始まったのですが、どうしても安い労働力のために外国から受け入れを始めたのでは?としか思えません。記事によると2017年11月に介護の技能実習がスタートしているようですが、まだ数百人しか来日していないようです。今やSNSで口コミはあっという間に広がります。「日本で稼げるからと聞いて来たけど、過酷は労働だし給料も多くない」という不満をもつ外国人労働者がたくさんいるとニュースで聞いた事があります。何のための労働者の受け入れか、政府にはもっと真剣に日本の将来を考えてもらいたいですね。
編集長インタビュー 日本マクドナルドホールディングス社長兼CEO サラLカサノバ
気になったコメントは、「プロパー社員の中には、登用されず、(外部からの登用に対して)複雑な心境の人もいるのでは」という問いに対し、「外部から人が来ることに対して脅威を感じる人は少ないと思います」と。さすがにこの質問を肯定する社長はいないですよね、笑。どの会社にも不満を持ったプロパー社員は必ずいます。外から来た人が、抜擢されたりすると、今まで発言するチャンスがもらえなかった古参人に不満がくすぶります。この問題の解決方法は、評価の透明性を上げるしかないのですが…、あと20年は日本企業は変われないだろうな~。
特集 シリーズ会社とは何か
今週は企業のM&Aで不幸になった人、幸せになった人のことが載ってました。人生何があるか分かりません。
買収されて、待遇が良くなる事もあれば、不幸になる場合もあるようです。今の時代、大手企業に入ったからと言って、未来が保証されているとはかぎらないので、若いうちに起業し、雇う側の立場にいる方がよっぽど望ましいのでは?と思ってしまいました。自身も実は会社のM&Aで人生設計が変わってしまったクチです…。幸い転職でき普通の生活を送れていますが、今もう一度M&Aがあったら、果たして生き残れるかどうか…。
スペシャルリポート 企業を救う裏仕事人
安全な日本で仕事をしているうちはピンときませんが、世界に目を向けるとテロとかで日本人が巻き込まれる被害が出ているそうです。そのようなことから身を守るため民間の諜報機関というのが存在するんですって。知らなかった…。VIPの身辺警護以外にも秘密情報の流出防止とかもしているという事には、驚きました。
ケーススタディー プリファードネットワークス
今は、猫も杓子もAI。AIを使わなくてもいい事までAI、笑笑。AIのロボットと通常のソフトのロボットの違いは、外から見てすぐわからない気がします。質の悪い深層学習やAIを提供する会社が増え、AIのイメージを悪くしてしまうのではと少々不安です。
たまたま今週号の世界の最新経営論にもAIの記事があり「AIやビックデータは現場を効率化するツールに過ぎない」と至極納得できる一言がありました。使い方を誤らないようにしないと。
他にも世界鳥瞰に、AI企業を悩ます倫理問題としてグーグルの記事がありました。兵器としての利用や、バイアスがかかったデータにより偏った判断を広めてしまう危険性があると。映画のマイノリティーレポートの様に、AIが危険人物と判断するようになる未来はちょっと怖いですね。
二人のカリスマ
松下幸之助さんの言葉がありました。「企業規模が大きくなり、何万人という人が働くようになると、もはや『ああせい、こうせい』と直接指導できるレベルを超えて、『無事でありますようにと、手を合わせてお願い』しないと部下は動いてくれない。」と。そんなたくさんの人の上に立った事がないので分かりませんが、なかなか言う事を聞かない部下より、二つ返事で動くイエスマンを周りに集める人の心境が分かった感じがします…。