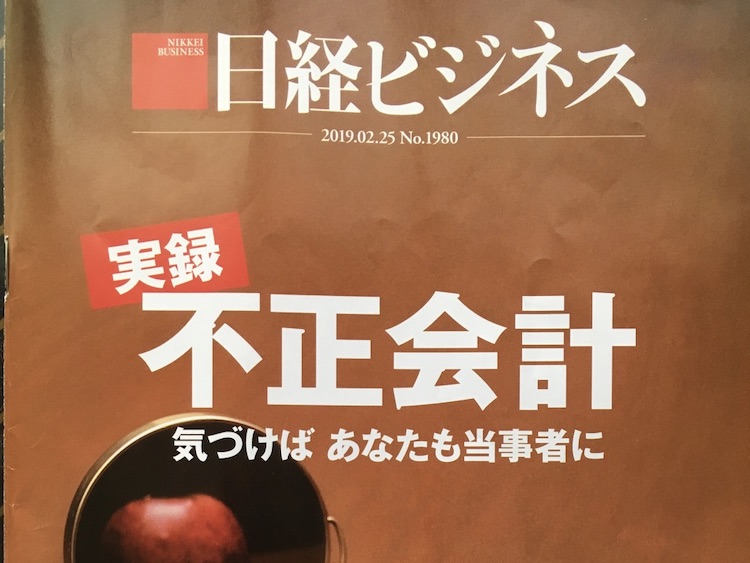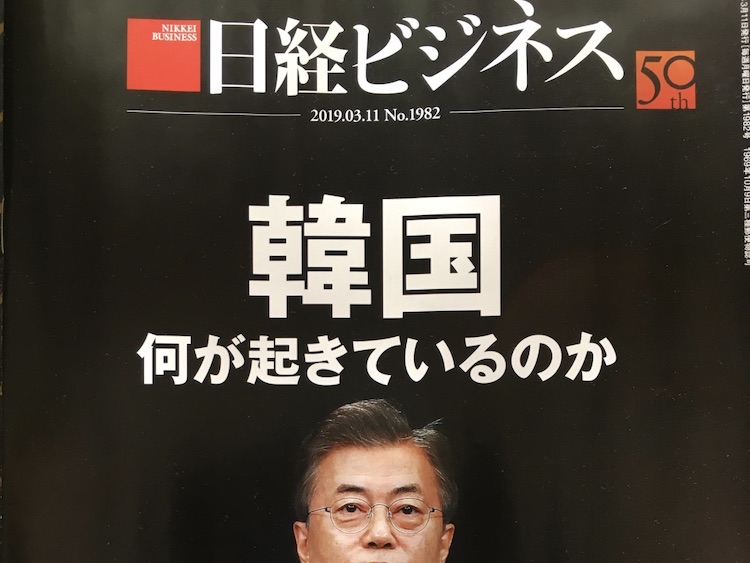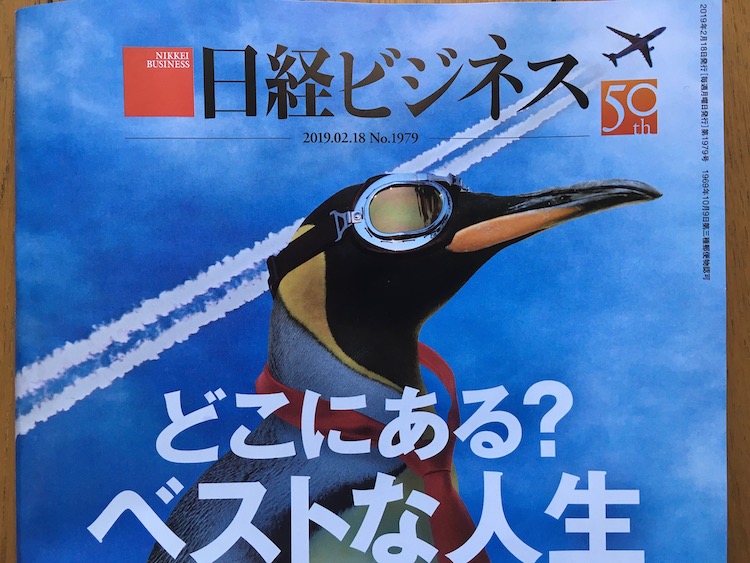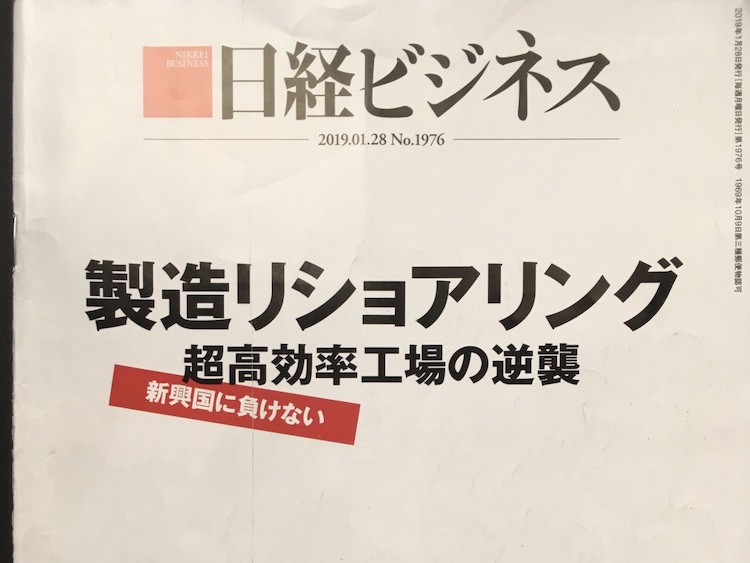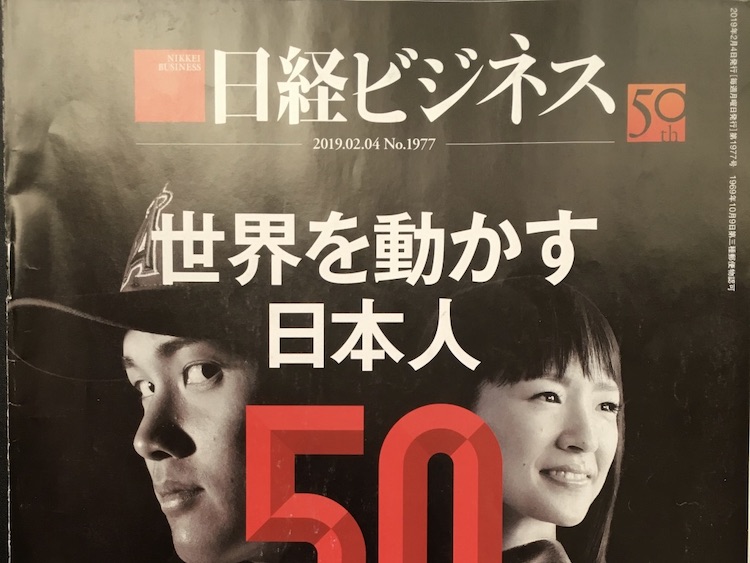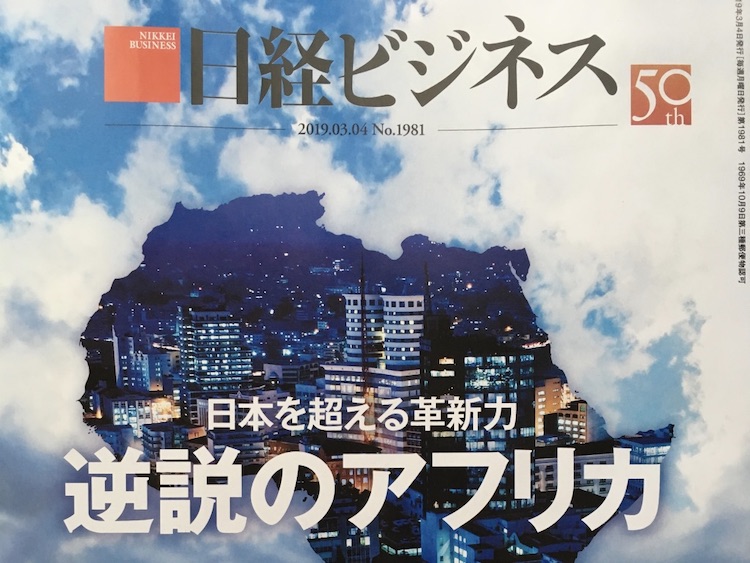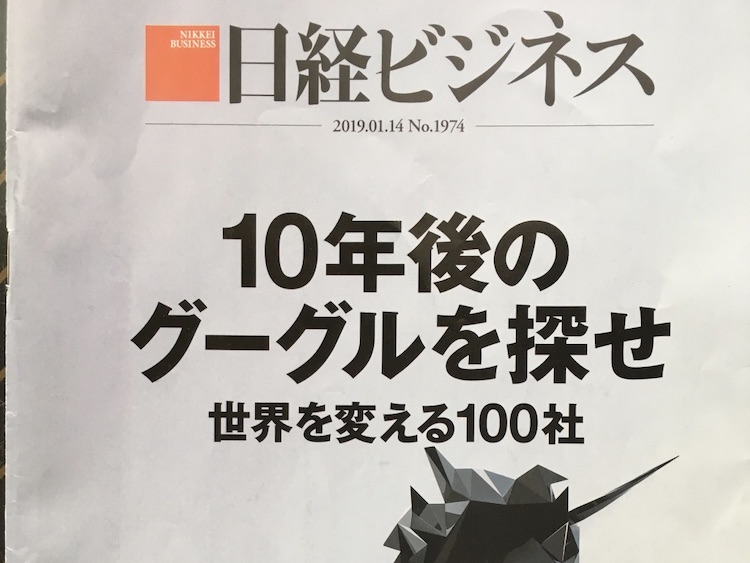有訓無訓
「自分が本当に正しい道だと信じたら、たとえ千万人が反対しても突き進む」:そう思います。ただ気になったのは「正しい」の定義。勝てば官軍という訳ではないけど、「上手くいくまでやる!出来た!=正しい判断であった」と考える人もいるわけで、時々それってありなのかな?と思う時があるんですよね~。そんな人が上司になった場合、当然納得いく説明がもらえるはずもなく…最終的には「いいから黙ってやれ!」と命令をもらうはめに。そういうことを考えると「正しい指示」ができる上司に出会えるかどうかって、とても重要だと思います。
不正会計
不正統計、不正検査、相変わらず出ますね~。日本企業の雇用形態は会社に対する愛社精神という無形の信頼関係の上に成り立っていることと、会社と個人が雇用契約を結んでいるという感覚が希薄ということから起きているのではないかな~と思います。「あなたのゴールはこれ」と契約のように決め、そのやった結果に対して正当な評価が与えられれば、愛社精神が上がるのではないかなと思っています。
とはいえ、ほとんどの会社が相対評価を導入しているため、納得できる評価をもらえる人は極めて少。潜在的な不正の温床はまだまだ残っていると思っています。
ケーススタディ BMW
アジャイル、これいいんですけどね~。問題は3つ。1つめは、できる人を必ず1チームに一人入れること。理由は簡単で、能力が低い人のチームで仕事が止まってしまうから(笑)。2つめは、そのできる人達が、各チーム間で連携を取れること。それぞれのチームが作ったものは完璧だけど繋げたら動かなかったなんて。3つめは、現地のビジネス商習慣に精通した人を用意すること。ヨーロッパの方では「0.01」の(.)テンに(,)コンマを使ったりするんですね。これを知らずに開発を進め日本に導入すると、1,000のコンマなのか、銭のことなのかわからなくなり後々困ります。困ってしまいます。
pie in the sky
細野議員が自民党の二階派に特別会員として入会するっていう話。前と言っていることが違うぞ?!ということに関して、笑いも交えてちくりと。思うに投票をする我々が、日本の政治に対して不信になり、もう誰がやっても変わらない、と無関心になりすぎたからではないでしょうか。視聴率が取れる不倫とかスキャンダルではなく「あの人は昔こんなことを言っていた」なんてことをもっとメディアが取り上げるべきだと思うんだけどな~。やっぱり投票するときは、過去から一貫して訴えていることが同じかを、きちんと見極める必要があると思いました。
2人のカリスマ
こんな風に考え方を変えられる社長は、一体何人いるだろうか…。「改革のリーダーシップを専務に任せ、もし成功すれば社員は、社長よりも専務の言葉に耳を傾けるようになるだろう」社長にとっては愉快でない話だが、「それでもいいではないか。良い土になればいい。花は咲いて、身をつけ、土に落ちる。良い土に落ちた実は、また素晴らしい花となる。そんな良い循環。。」
考え方を変えた社長も立派だけど、こういって社長を納得させた社長の嫁さんが一番素晴らしいってことか。
賢人の警鐘
「乗ると元気になるヒコーキ」こういう突飛な発想は、なかなかマネジメントに真面目に取り上げてもらえません。「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残るのは変化できる者である」ANAのマネジメント層のマインドが変化しているように思えます。上記の元気になるヒコーキはやっぱりビジネス、ファーストクラスをターゲットにしてんのかな…。エコノミーは少しでもいいからシートを大きくしてほしい。。