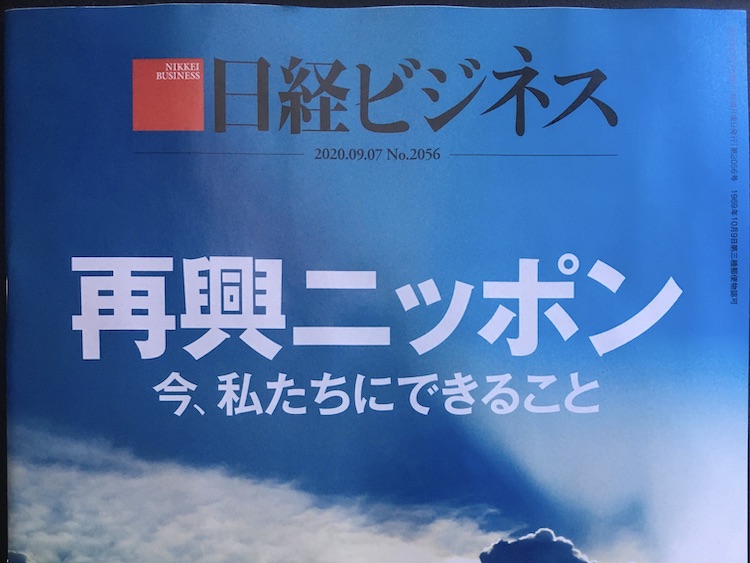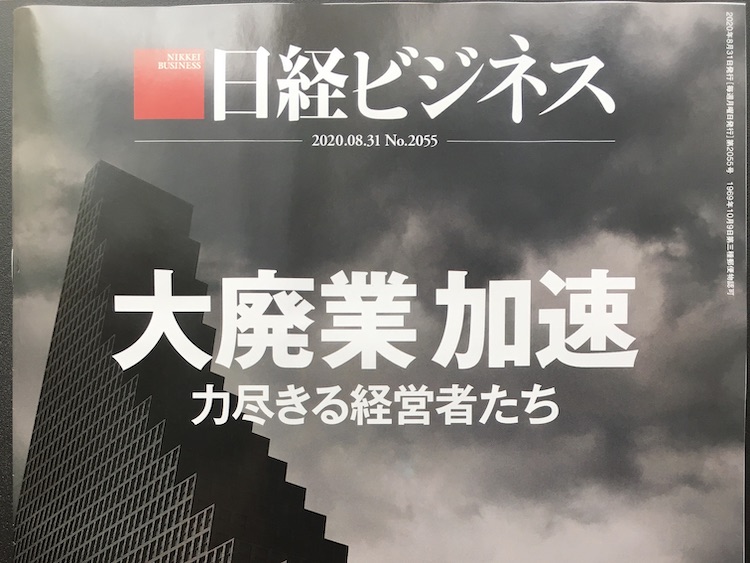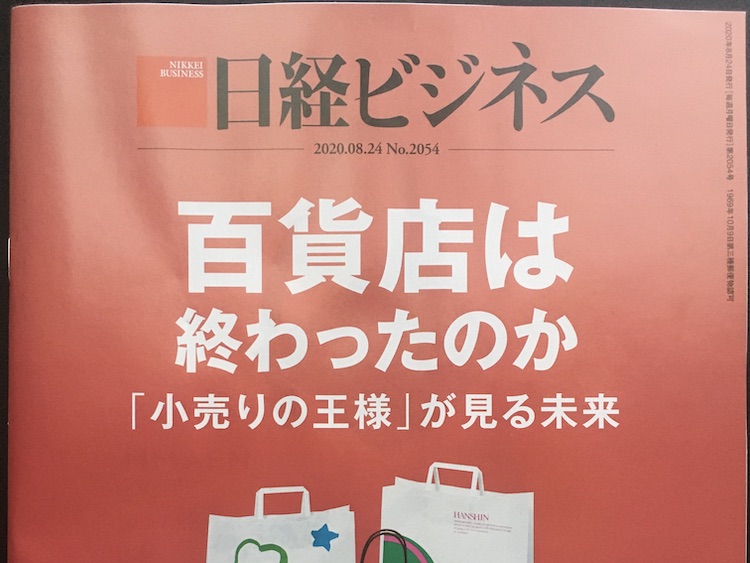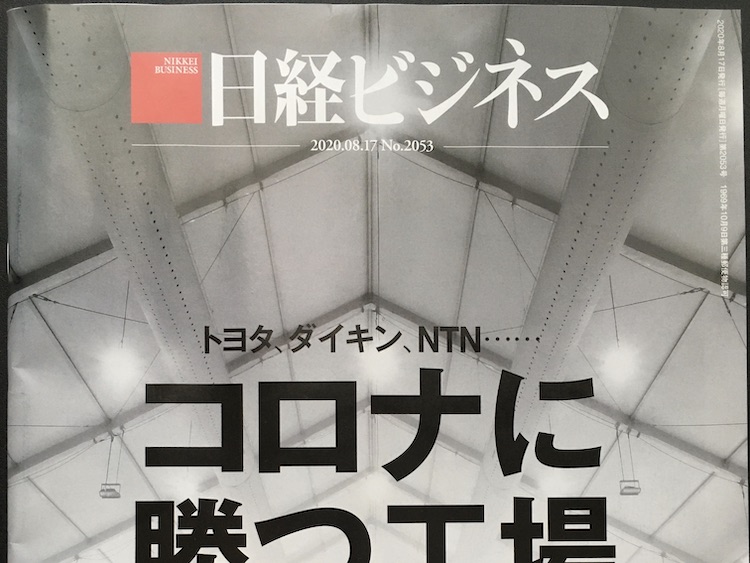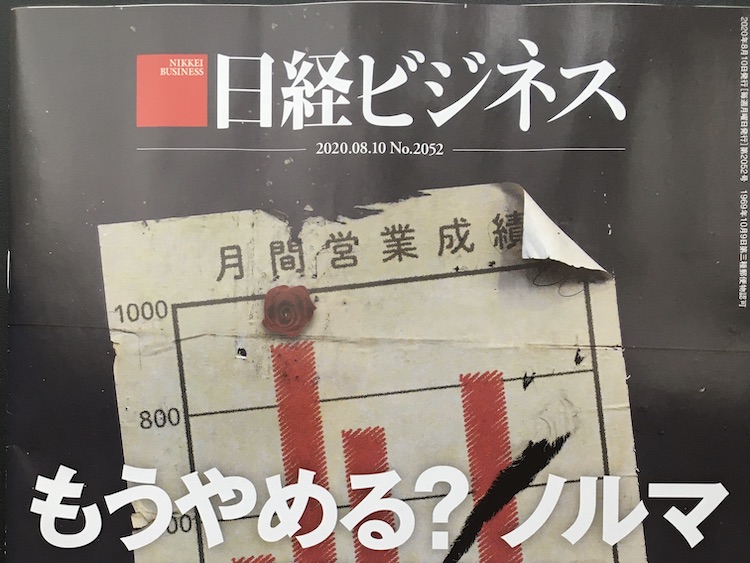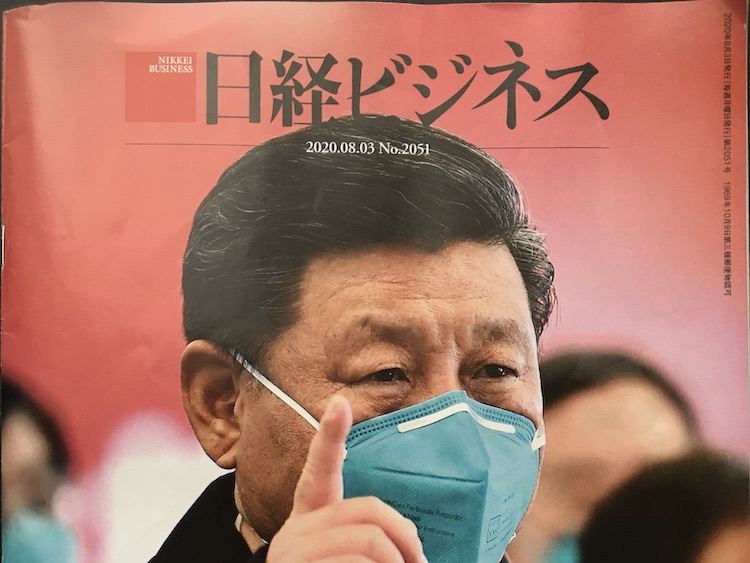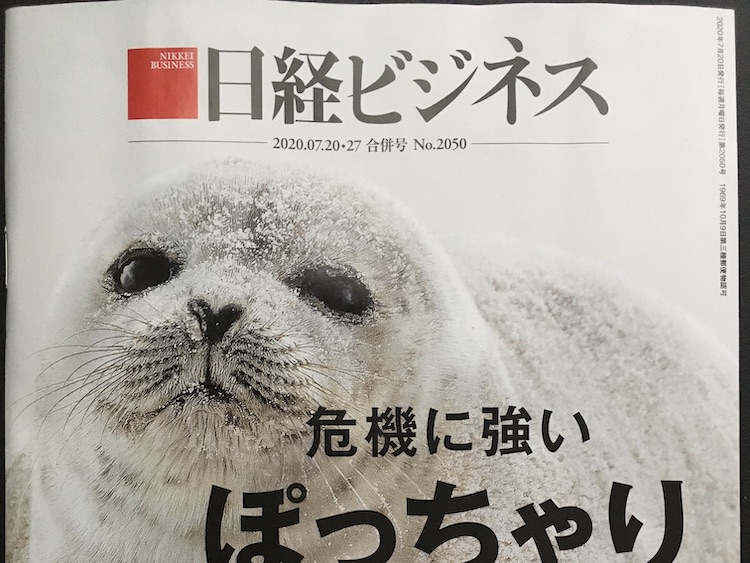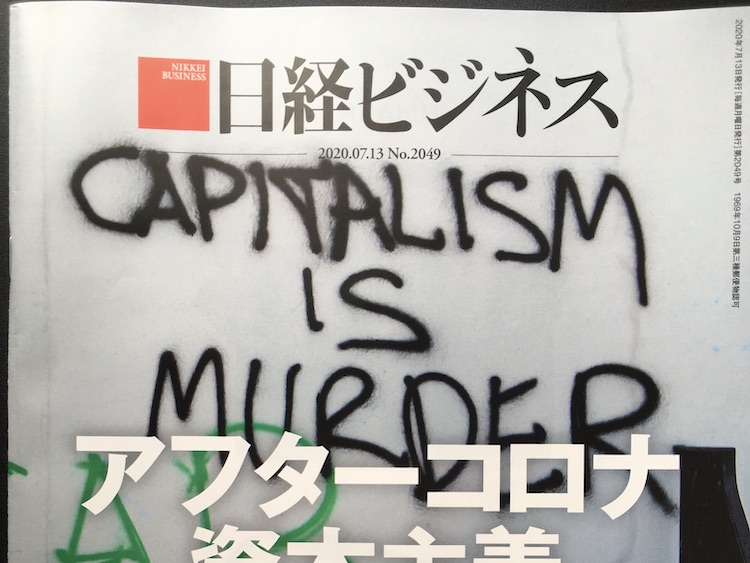有訓無訓 JT生命誌研究館名誉館長・理学博士 中村 桂子
「経済的な豊かさばかりでなく、当たり前の日常を、当たり前に暮らすことを大切に生きるようになる。そうなればお金や競争とは違う価値観が世の中を動かすようになる」ベーシックインカムが一つの手段だと思っています。特定の市や町でパイロットケースを始めてもいいような気がするんだけど。
ニュースを突く 外国人労働者から”切られる”日本
コロナ禍の影響で、外国人労働者の雇い止めが多発。安価な労働力として外国人を使う悪質な業者がいることは前から問題になっていました。今や、SNSであっと言う間に地球の裏側まで情報が届く時代。日本政府は、日本が嫌われていることを横目で見ているだけなのかな…。
時事深層 「低温」自民党総裁選、ポスト安倍と派閥の距離感 菅氏優勢、支持急拡大の内幕
「本来は政権の背後に控える国民の方を向いて仕事をするように指導しなければならなかったのに、現政権は人事権を盾に政権に忠実たれと霞が関を抑え込んだ」「見識ある政治家がリーダーとなって、政権と霞が関が共に国民を向いて仕事をするように変えなければなりません」年功序列や、派閥なんかを考えていたら日本がダメになってしまうのに…。そろそろ役人も政治家も通信簿を公開すべきだと思うな。
時事深層 山手線など終電30分繰り上げ JR、大都市圏でも運行縮小
日中の本数を減らすよりも終電を早めた方がコストを節約出来るんだ。
特集 変われるか?日本型雇用 働き方 ニューノーマル
隣の人の電話が鳴っていても取らないのがジョブ型。そもそも評価方法がきちんと定まっていないのに、ジョブ型に移行している企業がなんと多いことか。デメリットとかを知っているのかな?成果主義が、なんちゃって成果主義になったように、また日本独自のジョブ型なんてものができて失敗するんだろうな〜。あと、日本人の使う多様性って、自分にとって都合の良い多様性に感じる。年功序列や学歴で昇格した人がマネジメント層に多くいる会社は、コロナでもやっぱり変わりきれないと思う。フェアな処遇と評価、これが出来て初めて元気な日本なれると思う。
スペシャルリポート オンラインツアーから出張代行まで コロナ禍の不便 新ビジネスの芽育む
コロナで生まれた新しいビジネスの紹介。1つ目はオンラインツアー。個人的には、地元紹介の延長みたいなものであまり興味がわかないんだけど、それなりに需要はあるんだ…。リアルのツアーより参加者の平均年齢が低いってことにも驚いたし。2つ目は海外拠点にいる人材の活用術。コロナで仕事が減っているのは海外でも同じ。で、考え出した新しいビジネスが、海外の展示会等に出展する日本企業のサポート。海外に行けない人の代わりとなって、会場設営やオンラインのセッティングをするっていうビジネス。こういうのはうれしいかも。オンライン配信の特徴があったので備忘録として。
- 新規のお客にオンラインに来てもらうのはかなり難しいので、最初は既存のお客から始める。
- リピーターが多いものほどオンラインが有効。
- 退席しやすいため、長さは60分程度にする。双方向の会話が多くなるような場合はライブ配信。一方、商品紹介などは録画映像とチャットの併用。
ケーススタディー ジャパネットホールディングス 2代目経営、一気呵成の改革
高田社長の長男、二代目社長の話。創業者の功績が大きいほど次世代への引き継ぎは難しいと言われますが、自社の強み弱みだけじゃなくて、自分の強み弱みまでしっかり把握しているなと感心。社長になってからは、主に従業員の待遇改善。今でいうESGです。将来、ターゲット層の人口減が危惧されますが、着実な経営でまだしばらくは成長する気がします。
編集長インタビュー 野中 郁二郎 一橋大学名誉教授 経営は「生き方」を問え
国際競争力の落ちた原因は、「何事にも理論ありきで、『オーバーアナリシス(分析)』『オーバープランニング(計画)』『オーバーコンプライアンス(遵守)』に陥りました」と。 確かにオーバーという言葉が妙に当てはまる。オーバークオリティも、オーバーサービスとかも、笑。自分が思うに、人の評価方法が相対&減点方式だから極端にミスを恐れ、結果「自律分散的に試行錯誤しつつ前進」する人が減り、「人間の野性味から出る創造性、臨機応変に決断・実行する実践的知恵が劣化」したんだと思います。なるべくして指示待ち、イエスマンが増えたってことかな。では、どうすべきか?野中氏は「人間が本能的に持っている共感、エンパシーが重要」だと。シンパシーというのは分析が入るけど、エンパシーは入らないもので、無意識のうちに神経細胞が相手とシンクロするものらしい。「知識創造のプロセスは、まず共感があり、その上で同感し、それが対話に発展し、新しい概念をつくり、実践をしていくもの。最初に共感ありきなのが重要」。これをSECIモデルと呼んで提唱しているそうです。全体を通して、日本復活のカギになる素晴らしい記事だと思いました。ただ悲しいかな、本当に読まなくてはならない人ほど、こういう記事には目を配らないんだよな~。自己否定になるから…。
テクノトレンド 調理家電の新たな価値 低糖質で「コロナ太り」を防ぐ
糖質を減らす製品をメーカーが一生懸命開発しているという話。食べる量を減らせばいいじゃん?と思ってしまったけど、笑。
世界の最新経営論 バークレー流 成功するオープンイノベーション 怖いのは「プロパーの嫉妬」
協業における注意点がいくつか上げられていたので。
- あなたの株を持っていないし持つつもりもない。私にビジネスを盗まれるという心配をする必要もない。→相手を安心させること。
- 信頼関係をしっかり築き、資本以外の影響力を相手に与えた方がいい。→例えば、この会社との協業があってこそ自分たちは成長できると思わせるとか。
- オープンイノベーションは複数企業との協業が望ましく、共通基盤を作り全社を公平に扱うこと。
- 個人の尊重も大事。協業相手の画期的な提案は、時にプロパーの嫉妬や落胆を生む。
Pie in the sky ワイドショー発の清々しきループ
噂がうわさを呼んで、それがあたかも事実のように語られる…。ここ最近、そういう記事がどれだけ増えたことやら…。根拠不足だなと感じる時は、信用しないことが一番身を守る。
世界鳥瞰 米大統領選、醜い争いが招く危機
トランプ大統領の良かった点は、国民にくすぶっていた不満を表に出させたこと。ただ人の不安を煽り、その責任を他人にすり替えているのはちょっとね…。さてさて、次の大統領は誰になることやら。
世界鳥瞰 「次のテスラ」育てる中国投資家
中国でもEVが破竹の勢いで成長。「EV市場における外国勢との競争は、中国企業を鍛える事につながる。そして、長い目で見ると中国メーカーがグローバル市場を制するチャンスを高めるだろう」とありました。人口が10億ですからね、内需が大きいのが羨ましい…。政府も成長分野を後押ししているし。将来、中国の技術が世界のデファクトになってくるんだろうな〜。
世界鳥瞰 崩れ始めた東地中海の安定
「中国、ロシア、トルコなど、力をもって既存の国際秩序を破壊しようとする修正主義諸国。過去の約束をほごにしようとする米国、地政的問題の解決に強硬手段を取ることに消極的な欧州。」小競り合いから大きな世界大戦にならないことを祈るばかり。国家という枠があるから争いごとが増えるんだよな…。住んでいる国とは別のつながり、デジタル国家というものが本当に出てくるんじゃないかと思ってしまう。
賢人の警鐘 英エコノミスト誌 元編集長 ビル・エモット
米中の断絶により、中国の独自進化がガラパゴス化してしまうのではと危惧。ん〜、個人的には、その中国のガラパゴス技術がグローバルスタンダードになるんじゃないかなと思っています。だって一番成長しそうで潜在的な需要が大きいのは中国ぐらいなものだから。むしろ気になるのは、米国が、中国と米国どちらを取るの?と踏み絵を求めてきそうで怖い。