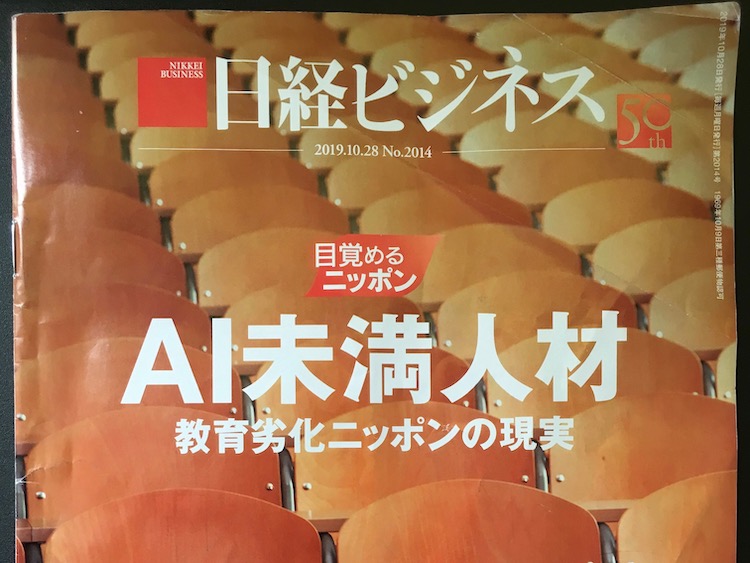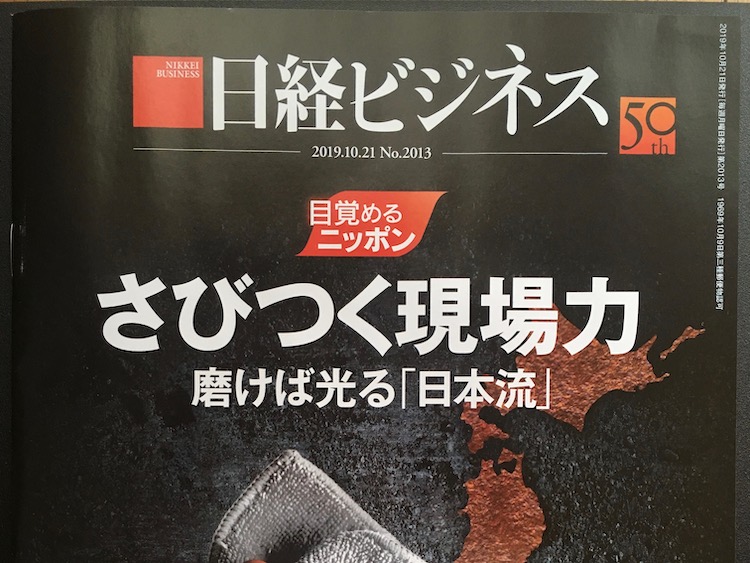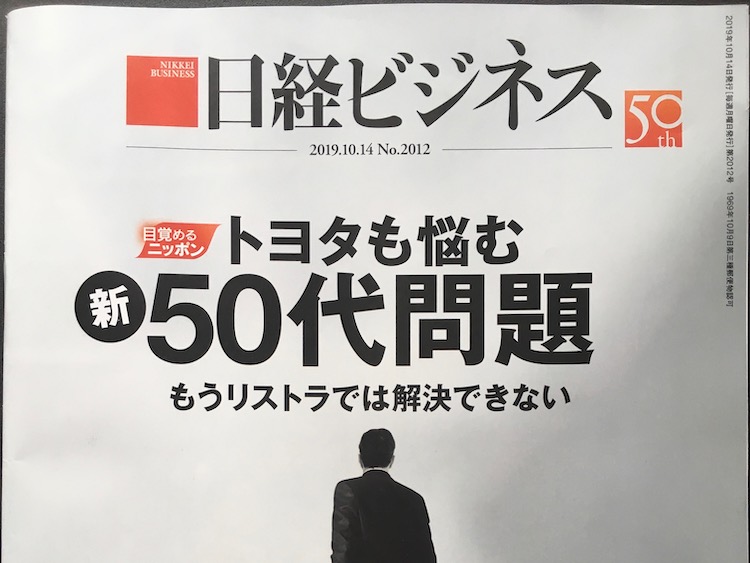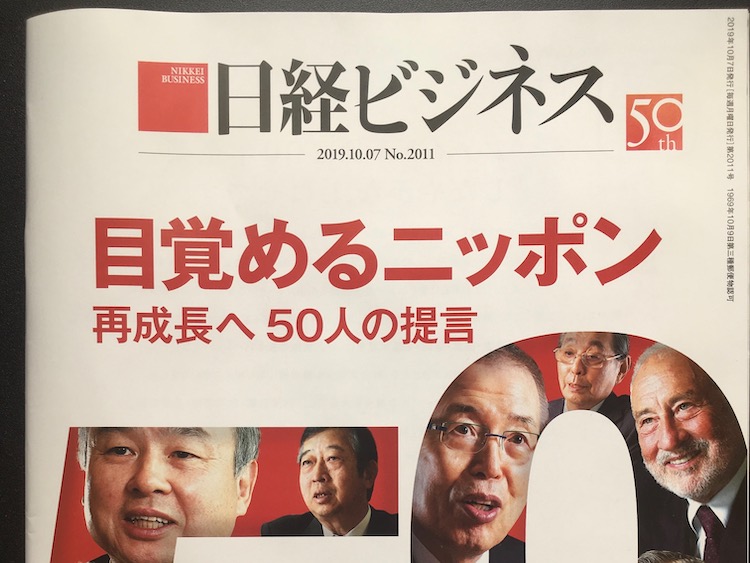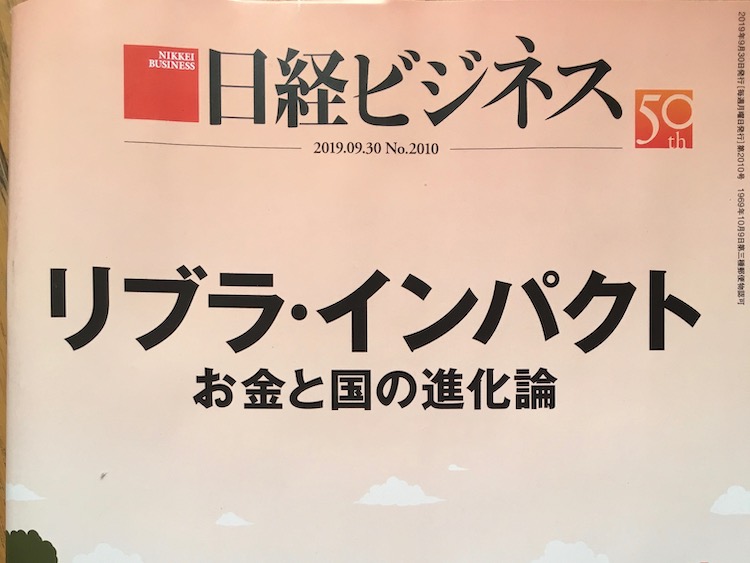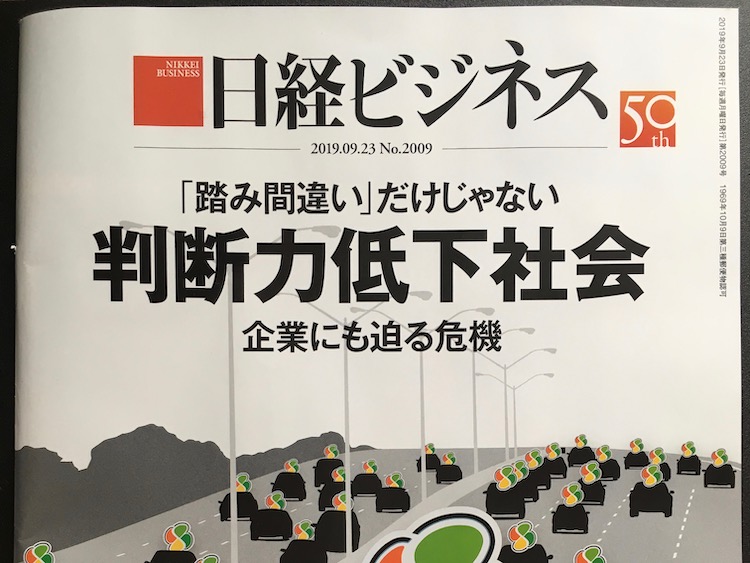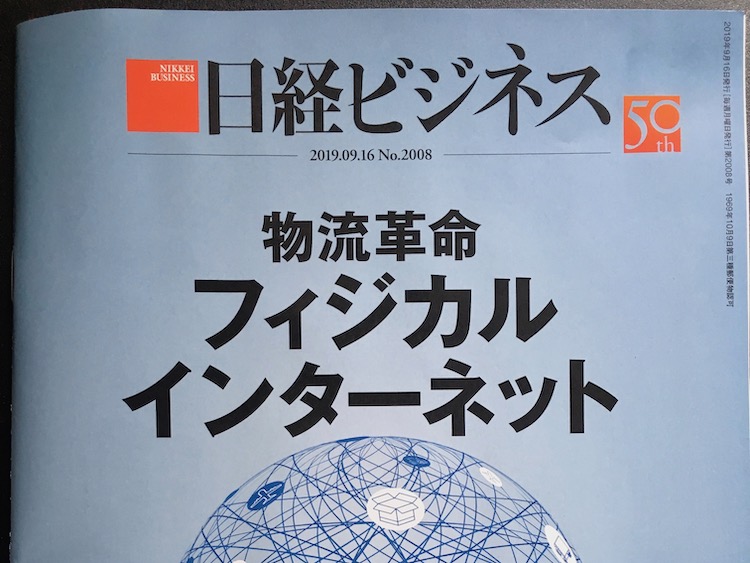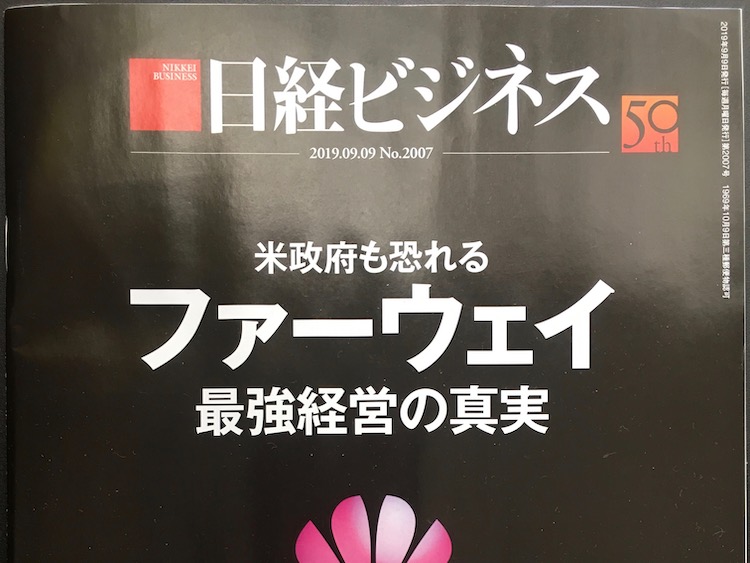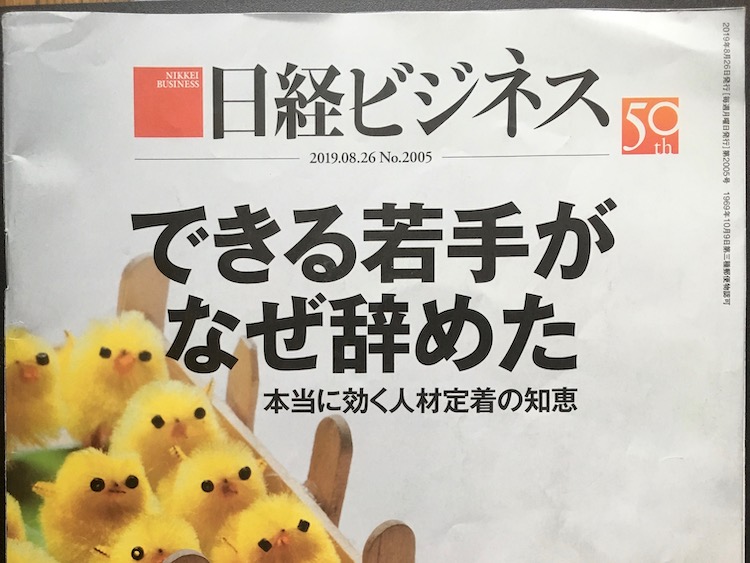有訓無訓 徳地立人
自分がいつも悩むのが、「手間の割には儲けが少ないビジネスを積極的にすべきか」ということです。この記事の徳地氏は、大企業から信頼を得るため、小さな仕事でも積極的に取り、結果、大きな仕事に取る事が出来たようです。最近は成果主義を取り入れている会社がほとんどです。売上至上主義ではなく、小さい仕事でもコツコツとしている人を評価する仕組みがあると嬉しいですよね。とはいえ、お客との付き合い方がドライになっている昨今、今後もこの様な地道なやり方が有効なのか気になるところです。
時事深層 インバウンド減、消費増税に追い打ち
インバウンドで延命できただけで、百貨店単独での生き残りは、難しいような気がします。特に地方百貨店は、地域社会と一緒になって、百貨店のあり方、方向性を探る必要があると思います。逆に都心の百貨店は、今後もインバウンドの恩恵を受けることができるので、日本でしか買えないもの、例えば工芸品なんかをメイン商品にするのも手段ではないでしょうか。
時事深層 ダイソン撤退、中国では販売急減 始まった淘汰、EVバブル崩壊か
給電インフラが整ってないし、満充電に時間がかかるため、なかなかEV車が普及していません。数分でフル充電できるようなブレイクスルーがない限り普及はまだ遠そうです。まだしばらく内燃機関が続くかな。
時事深層 店内飲食シールで摩擦解消
コンビニとかの店内で食べている人に、10%の消費税を払っているか?とわざわざ聞く人がいるんですね。まあ、一番の問題は、複雑な制度を立ち上げたことだと思う。
時事深層 国内の販売台数9年で10倍 アメ車は売れず覆したジープ
車がある生活シーンを上手く訴える事が出来ると、まだまだ車は売れる、という事を示した事例でした。モノがあふれる時代は、このシーンの提案も購買の決め手になってきます。
特集 AI未満人材 教育劣化ニッポンの現実
IMD世界競争力ランキングで日本は、調査開始以来最低の30位。ビジネスの効率性にいたっては、46位。競争力の低下は、日本の環境だと思います。今ある物で必要十分。不便さが少ない。だからさらに良いものが生まれにくい。同じように仕事をしているのに、出世するのは優秀な人でなく、世渡り上手や良い大学を卒業している人で、やっても無駄だなって。
子供は高校ぐらいから海外に行かせるべきかもしれませんね…。
少々心配するところが違うのでは?と感じたのが、通年採用が当たり前になると、新卒の就職浪人が増えるかもしれないと。むしろそういう状況になれば、学生も在学中にもっと勉強するようになり、良き循環が生まれそうと思うけど、どうかな。
スペシャルリポート TEAL組織
TEAL組織を分かりやすくいうと、フラットな組織という事になりますね。昔ながらの上位下達の日本の企業には、忖度がある以上、うまく機能しない気がする。
テクノトレンド
個人に合わせてオフィス空間を快適にしてくれるのは嬉しい。ただ、「オフィスに移動する」という行動そのものが生産効率を下げているから、在宅勤務をもっと使えるようにしてほしいね。
編集長インタビュー 資本主義の変質に戸惑うな 東レ社長 日覺昭廣
「投資家と投機家、株主資本主義と金融資本主義を分けないといけない」。そうそう。投機家は、短期的な金儲けしか考えないから、会社のビジョンと合わないなら無理な注文は堂々と断ってもいいと思う。あとは積極的な情報開示。透明性があれば、ああしろ、こうしろは減ると思います。
社外取締役の考え方「知らない人が何をできるのか。よく知っている人が倫理観正しく観る」その通りだと思います。「大事なのは結果であって制度や形ではない」と。社外取締役を入れたり、第三者委員会を設立するのは、倫理観を持ったトップマネジメントが減っているということの裏返しではないでしょうか。忖度、世渡りで出世した人は、自分を引っ張ってくれた人に「ノー」と言えないので、他人を使って、自分の上司の過ちを指摘しているのかな。
世界の最新経営論 ハーバード流 プラットホームビジネス
備忘録として。
当たり前だけど、安心して取引できる仕組みを作る。素早く市場に参入し、プラットホームの切替えコスト(スイッチングコスト)を高くすることによって、競合の後発を防ぐ。
世界鳥瞰 中国で広がる学校教育拒否
世界の標準というものはなんだろう?自分達は、世界標準なんだろうか?と考える中国人が徐々に増えてきている証拠なんでしょうね。中国がオープンになるのも時間の問題のような気がします。嬉しくもあり、恐ろしくもあり…。