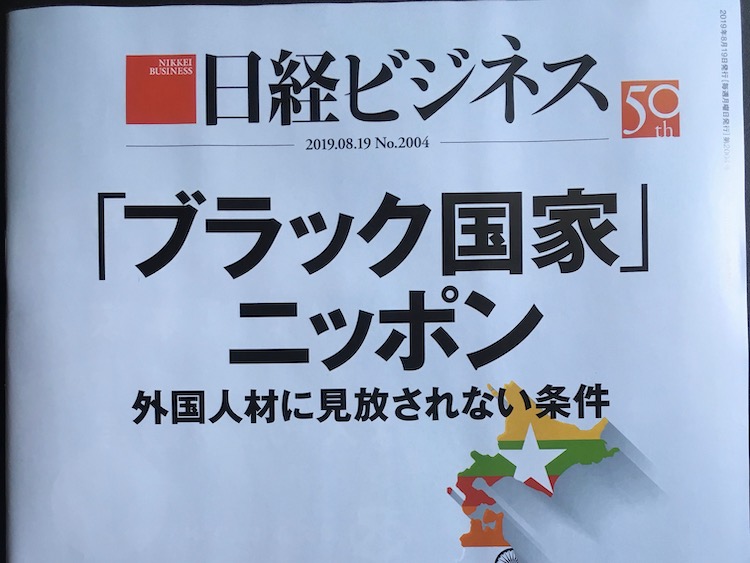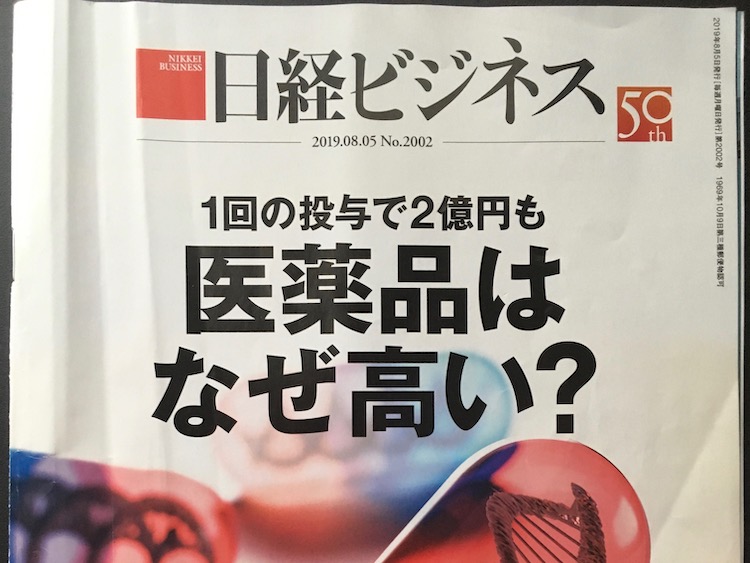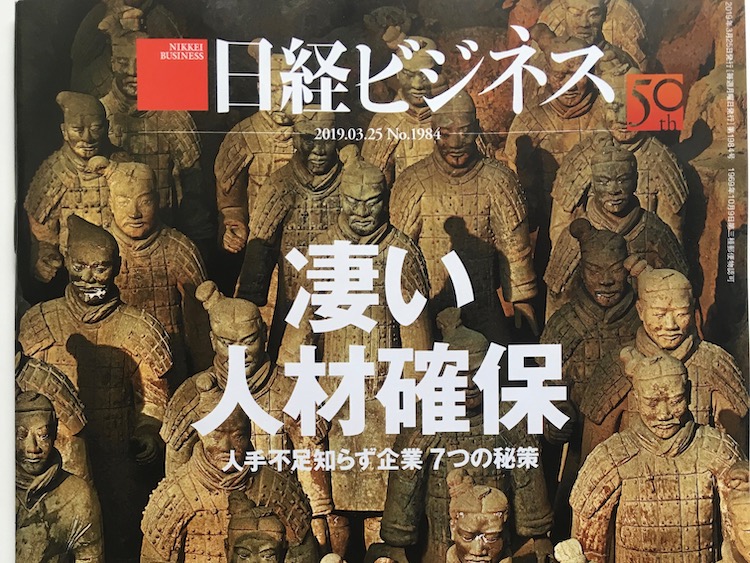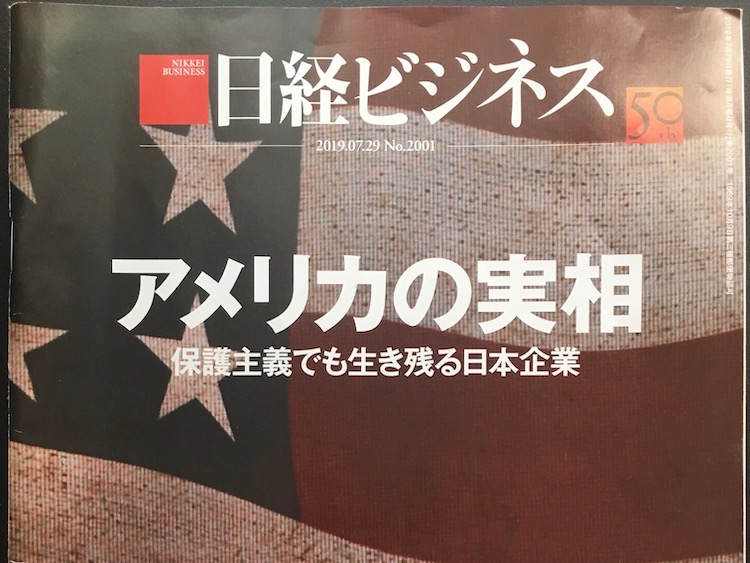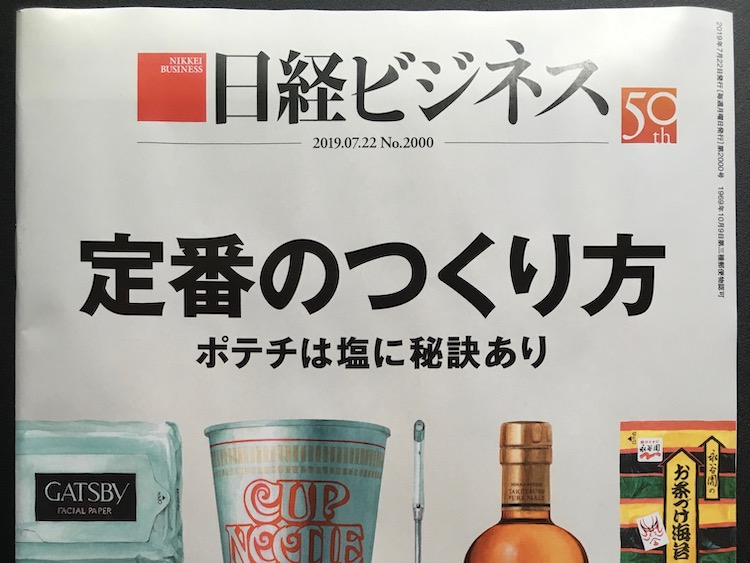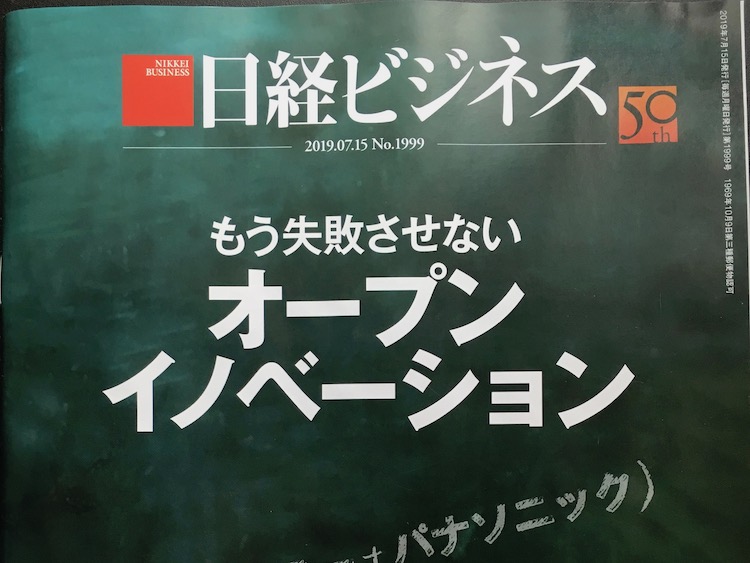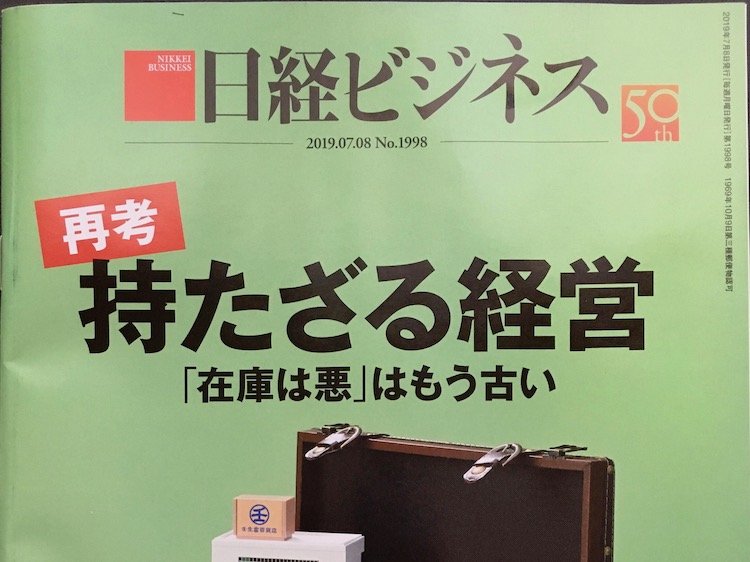有訓無訓
二宮尊徳の言葉で、積小為大。小さな努力を、コツコツと。ちゃんと熟語があったんですね。
編集長の視点
日本の製造業の現場では、英語を受け入れる下地がないため、海外から人を入れようとしても、うまく回っていないようです。経営層は、外から優秀な人材を入れたい。でも現場は、その優秀な人とうまくコミュニケーションが取れない。このミスマッチを減らすためには、まず人の採用よりも、どうやって今後生き残っていくか、社員全員が共通の危機感を持つところから始まるような気がします。
ニュースを突く
「簡単な足し算、引き算さえできれば、廃炉と第5次エネルギー基本計画がどれほどかけ離れた計画になっているのかすぐ分かる。もっとまともな論議をすべき。」との記事でした。政府の問題先送り。今は解決方法がないだけ。将来きっと誰かが魔法を使ってなんとかしてくれるさ、と思っているんですよ。
時事深層 国内大手の業績が軒並み悪化 自動車部品、先の見えない三重苦
互換性がない部品だから、こういう問題が起こると思う。上位下位互換がソフト、メカどちらもできるようになれば、部品メーカーは、死蔵品を抱えるリスクが減るし、また自動車メーカーにしても、古い車の性能をよくできるので、いい事ばかりなのに…。個人的には、車の交換部品が少々違っていたとしても車として機能すれば全然気にならないのですが。
EVカーになれば、この発想は取り入れやすくなりそうな気がしますが…。
特集 ブラック国家ニッポン 外国人材に見放されない条件
1位のドイツ、2位のアメリカと比べると桁違いですが、それでも3位の英国に続き、日本は4位の40万人。人材不足を補うため多くの外国人を移民として受け入れているんですね。
そもそも給料を高くすれば外国人に頼らず日本人でも人が集まると思うのに。自分たちが生き残るために、低賃金で働いてくれる外国人に流れるのは、何かが違うと思います。如実に表しているのが、外国人が働きたい国、地域ランキング。日本は対象34国の中で下から数えて2番目の32位。社会の閉塞性、定住しにくい、収入が低い、ワークライフバランスが悪い、子供の教育環境が悪いが主だった理由で、村社会が残っているのを感じます。今やSNSで悪評はあっという間に広がります。政府が、外国人労働者の不満に対して適切なケアをしなかったばかりに、今後長い時間をかけ、そのツケを払う羽目になりそうです。
スペシャルリポート ここまで進んだ小売り、物流のRFID活用 普及の条件が分かった
RFIDの普及に時間がかかり過ぎると、それに変わる製品が出てきちゃいそう。例えば、印刷できる無線タグとか。
ケーススタディー 朝礼で褒める、社員を生かす 寿スピリッツ
自分も、学生の頃にしていたバイト先で、同じ様に経営理念を覚えさせられた記憶があります。サービス業ではバイトテロを封じ込める策として、効果的かもしれません。
テクノトレンド
ガンは遺伝子の変異が原因になっているとは知っていたけど、同じ臓器のガンでも患者ごとに遺伝子変異が異なるとは知りませんでした。最新の治療薬でも、その遺伝子変異と適合しないと効き目が薄くなってしまうようです。どうやってその変異を特定するか、それもガン攻略ポイントになってくるようです。
世界の最新経営論 気鋭の経済論点 リブラに見る通貨と国家の関係
リブラが発行されれば、手数料が高い銀行のあり方を根底から変えてくるので、貧乏な私には良い事だと思っていたけど、国家ではなく企業がガバナンスを見るのか。その企業の決定で経済が左右されるのは嫌だな…それは問題だ…。こうなる前に、各国が足並みをそろえて国際統一暗号通貨を出してもらいたかったな。
新社長初心表明 三井住友フィナンシャルグループ 太田純
約30年前、私が新卒で入った会社の当時の課長も「カラを破ろう」と言っていました。未だこの言葉が出てくるのは、やっぱり日本企業は、上にモノを申せない雰囲気が根深く残っているんだろうなと思いました。相変わらず忖度部下が出世しているんでしょうね。
賢人の警鐘
「連続性と横並びで生きてきた日本と日本企業は、不連続、非連続な世界に対応する術を持たなかったと言える」同感です。この人のコメントは、歯に絹着せぬ物言いで好きですね。ただ不思議なのは、大抵、こういう人は嫌われて会社を追い出されるのに、なぜ生き残れたのだろうか…。そっちの方が気になってしょうがない、笑。